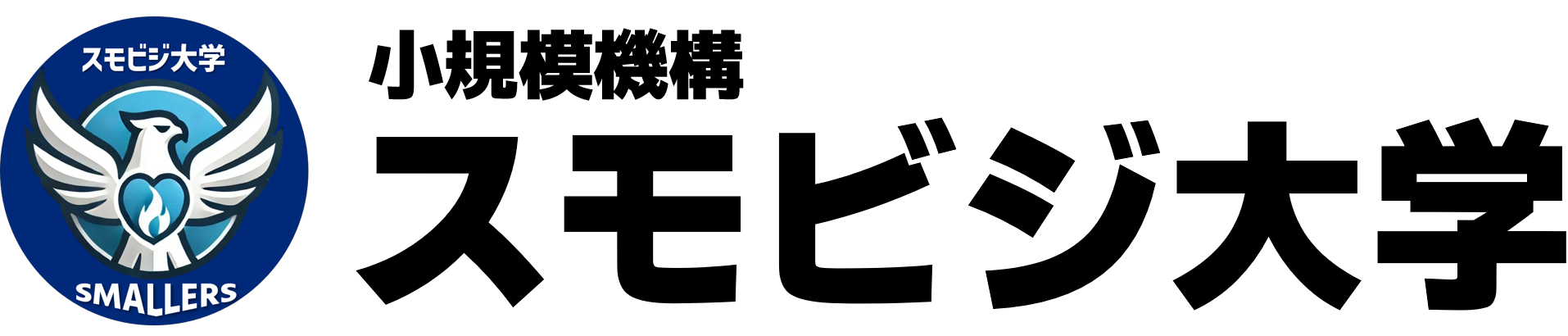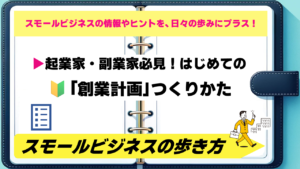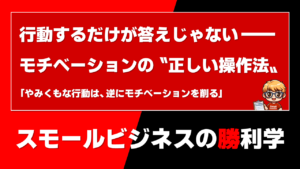『十人十金』第一回:業務コンサルティング社長の場合/失敗談(前編)
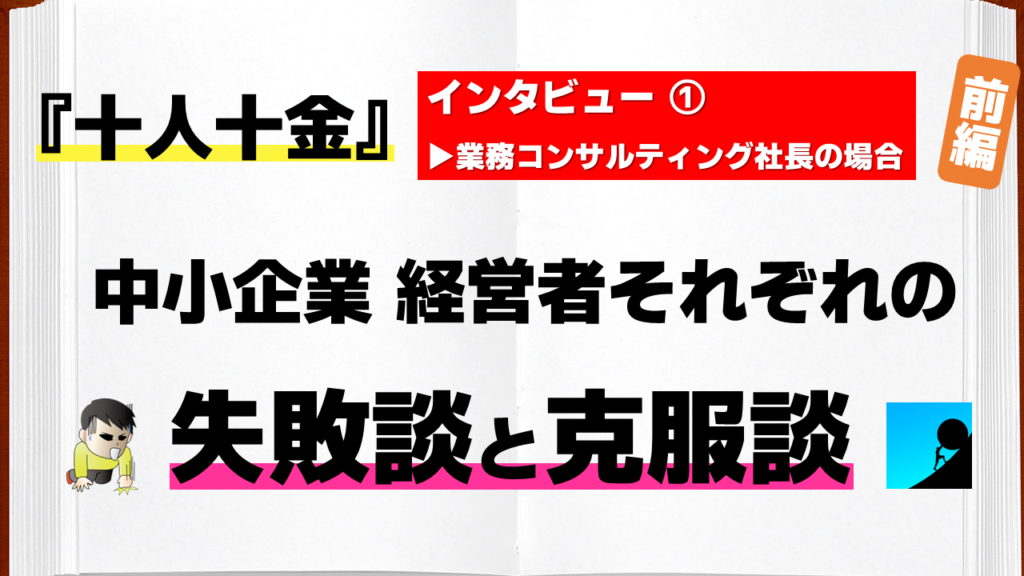
・インタビュー対象者:山本 健一さん(仮名)※以下、山本さんと表記
・失敗年齢:31歳(当時)
・筆者:スペース・テラ/てらもと さとし(スモビジ大学長)
筆者:「経営には成功と失敗があり、そして失敗の裏には必ず理由があります」順調に進んでいた事業が、一つの判断ミスで崩れ去る…それは決して他人事ではありません。本日は、中小企業経営者のリアルな失敗談をお届けします。事業を軌道に乗せながらも、ある出来事をきっかけに経営が破綻してしまった山本さん。その転落の過程と、そこから得た教訓とは?
『小さな事業を大きな主役へ』ようこそ、スモビジ大学へ!こんにちは、皆さん!学長の寺本 智(てらもと さとし)です。
私はこれまで10年以上にわたり小規模経営の分野で活動、200社以上のスモールビジネスをサポートし、500を超えるの案件を達成してきました。
細かくお伝えすると、これまでにサポートした企業は225社です。中には「1,000社以上サポートしました!」という方もいますが、小規模企業の多岐にわたる課題に本気で向き合うと、この数字が限界だと実感しています。それだけ、1社1社に丁寧に寄り添ってきた結果だと自負しています。
それでは早速、『十人十金』をご覧ください!
「順調なはずが、負の連鎖が始まると止まらなくなった…」
筆者:本日は現在、中小企業を中心に個人でプロジェクトマネジメントを手掛ける経営者の方にお話を伺います。当時は業務コンサルティング会社を経営していたと聞いています。もともと介護職員から独立し、事業を軌道に乗せるも、大きなトラブルに見舞われたとのこと。まずはその経緯をお聞かせください。
山本さん:はい。私はもともと理学療法士として介護業界で働いていました。しかし、経営陣の方針に疑問を持つことが多く、自分の理想とする経営を実現したいと独立を決意したんです。
筆者:なるほど。しかし、独立する際に介護事業ではなく、コンサルティングの道を選ばれたのですね。
山本さん:そうなんです。介護業界全体の将来性に疑問を感じていたのと、ファイナンシャルプランナーの資格も持っていたことから、お金や経営に関わる仕事をしたいと思いました。ちょうど先輩に経営コンサルタントの仕事をしている方がいたので、そのノウハウを学びながら、業務コンサルティングの仕事を始めました。
筆者:スタートは順調だったとか。
山本さん:はい。当時、国が推進していた「企業主導型保育事業」のサポート業務が大きな収益源になりました。保育園の設立や日々の申請業務を請け負うことで安定した収益を確保できていたんです。そのおかげで介護事業所の業務コンサルだけでなく、幅広い業種の案件を受注できるようになりました。
筆者:そのまま順調にいけば良かったのですが……。
山本さん:そうですね。1年目は黒字決算で、その勢いのまま、2年目には新たなチャレンジとして飲食業に乗り出しました。幅広い業種の業務コンサルティングをしていたので、飲食店の経営にも自信がありました。予測通りこれも最初は順調で、多業種経営が成功していると思っていました。しかし、思わぬところでトラブルが発生したんです。
「丸投げ運営が招いた破綻のはじまり」
筆者:何が問題だったのでしょうか?
山本さん:実は、業務コンサルティングで関わっていた介護事業所の1つが、私のサポートのもとで保育園を運営していました。その保育園の設立から申請業務まで、すべて私の会社が支援していたのですが、運営方針について介護事業所の母体と対立してしまったんです。
筆者:具体的にはどのような対立だったのでしょう?
山本さん:母体の介護事業所側は、保育園の経営にそれほど関心を持っておらず、私たちに運営を任せきりでした。非協力的だったと言っても過言ではありませんでしたね。当時は保育方針なども私の会社で決めていました。それなのに、決めたことには根拠なく批判してきたりで…次第に対立が生まれるようになりました。私どもは運営に関して一任されている、いや、丸投げ状態にも関わらず後出しジャンケンのように、あれこれ言われるのは違うと。しかし、こういった運営方針の不一致が生じたことで、どちらの指示を優先すべきか現場のスタッフが混乱し、次第に保育士たちの離職が相次いでしまったんです。
筆者:それは現場にとっては非常に厳しい状況ですね。
山本さん:ええ。保育士が減ると当然ながら園児や保護者への対応も手薄になり、クレームも増えていきました。その対応に追われるうちに、別の事業である飲食店にも悪影響が出始めました。飲食業は管理不足や人手不足が直撃するとすぐに売上に響くので、負の連鎖が始まってしまったんです。今になって思うともう少し私も大人になって良かったとも思いますが…若さもあったりで。何よりその介護事業所は私の前職場でもありましたから…方針については引くに引けないところがあったんだと思います。
筆者:なるほど。そういった経緯があったんですね。
山本さん:はい。いくら不満があった前職場とは言え、今は仕事をいただいてるクライアント。その意識が当時の私に足りてなかったんだと思います。また〝日々のコミュニケーションを通じて、関係者やスタッフ仲間と意思疎通を図ること〟がいかに大切か、をこの経験で学びました。
「追い詰められた資金繰り、そして終焉と破産へ」
筆者:資金面での影響も大きかったのでしょうか?
山本さん:はい。離職者が相次いだことで保育園の運営に人員を割いてしまい、人手不足と管理不足が原因で飲食店の売上が落ち込みました。さらに私自身も保育園運営のトラブル対応で時間と労力を取られ、業務コンサルティングの本業にも影響が出始めました。その結果、資金繰りが急激に悪化し、運転資金の確保が必要になりました。元々は園児の確保が思うように行かなかった場合を想定して、保育士の働く場所の受け皿として飲食業を始めたのもあるんです。保育士の確保は難しく、園児が増えてから採用を試みても遅いケースがありますので。しかし当時の場合は完全に本末転倒でした…
筆者:そのタイミングで資金調達を?
山本さん:はい。設立2年目の会社だったので、500万円の融資を日本政策金融公庫から創業扱いで受けることはできました。しかし、本来であれば設備投資や広報活動費、人員強化に使うべき資金が、単なる資金繰りの穴埋めになってしまったんです。半年も経たないうちに資金が底をつき、再び資金難に陥りました。
筆者:まさに典型的な「自転車操業」ですね。
山本さん:その通りです。資金繰りに追われる日々で、肝心の現場改善には手を付けられないまま、さらに状況が悪化していきました。湯水のごとく資金が減っていく様は、今でもはっきりと覚えています。しっかりトラウマになりましたね…
筆者:そこで起死回生を狙った策が?
山本さん:自社で新たな保育園を設立しようとしました。しかし、計画の甘さが露呈し、準備段階で頓挫。こんな状態でいい計画ができるはずがありません。荒唐無稽な話です。業務コンサルティング会社なのに、情けないものです…新たな資金調達も試みましたが、当然ながら金融機関からの追加融資は受けられず……最終的に会社は倒産し、チームも解散することになりました。
筆者:短期間での急成長も仇となった形ですね。
山本さん:はい。順調に見えていた1年目とは打って変わり、2年目には負の連鎖で一気に崩れてしまいました。本当に早かったです。「転落」していくって表現がぴったりです。それはもう、もの凄いスピードでした。経営ってこんなにも早く転がり落ちていくのかと思いましたね。今振り返ると、事業拡大のスピードとリスク管理のバランスを考えなかったことが致命傷になりました。
筆者:自己破産も経験されたとか?
山本さん:500万円だけじゃ足りなくて、消費者金融からも借金してましたから。通常の金融機関は相手にしてくれませんでしたし。そういった借金って金利が高いのもありますが、精神的にこたえるんですよね。〝自分が健全じゃない〟みたいに思えて。本当にもう苦しかったです。そういった苦しみからも解放されたい気持ちが強くて、最終的に自己破産を選びました。まさか自分が自己破産をするなんて思いもしませんでした。数億って借金じゃなく、結果数百万の金額で…結婚したばかりというのもあって、家族や親族に素直に頼れなかったのもありました。当時のコミュニケーション能力の無さを悔いるばかりです…
筆者:非常に貴重な経験談をありがとうございました。では、この苦境からどのように立ち直ったのか——次回、克服編で詳しくお聞きしたいと思います!
次回予告:「倒産を経験し、すべてを失った山本さん。そこからどうやって這い上がったのか?どん底からの逆転劇…彼は何を学び、どう行動したのか?」次回、克服編で明かされる——希望の光が差し込む瞬間!」