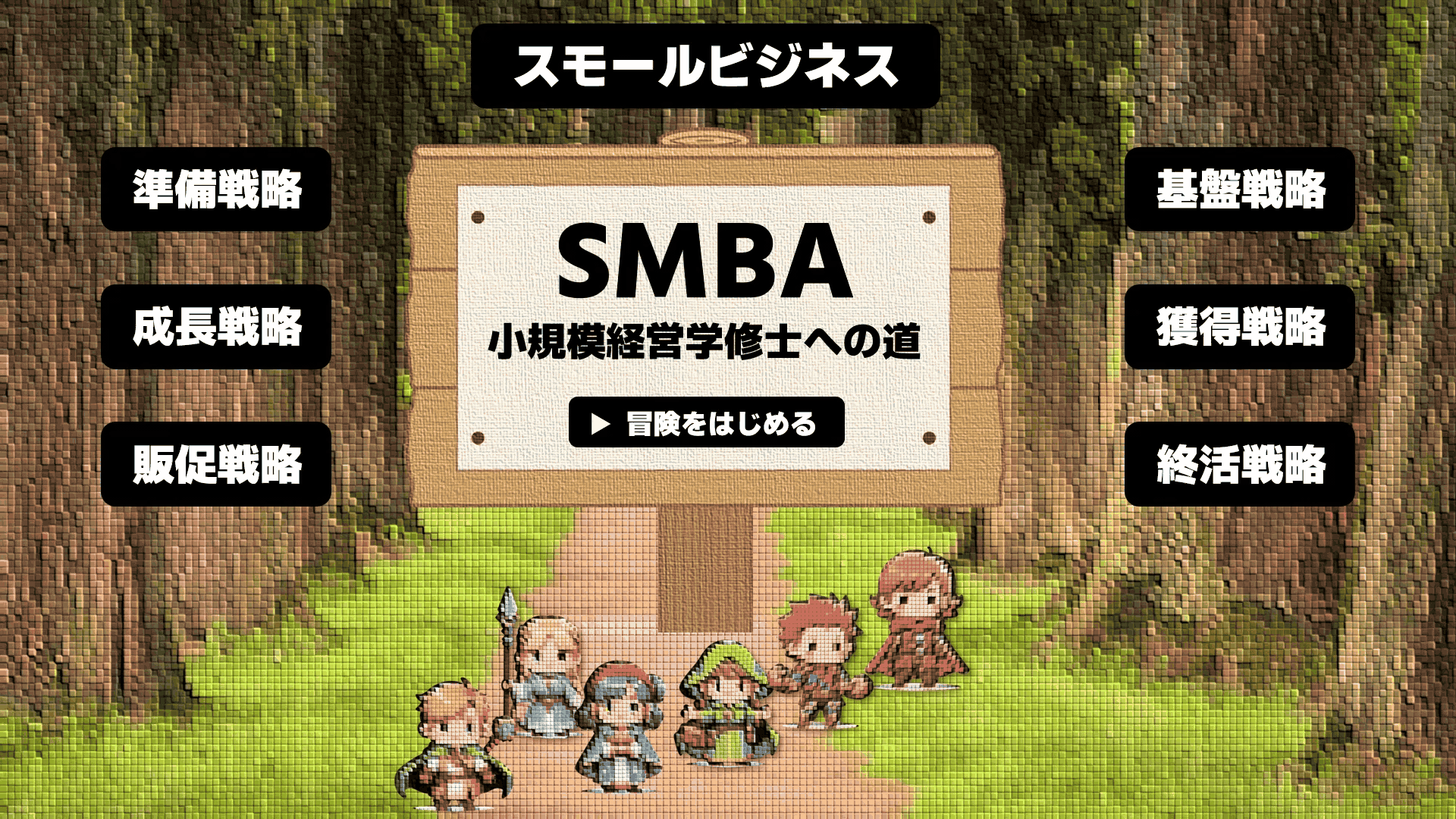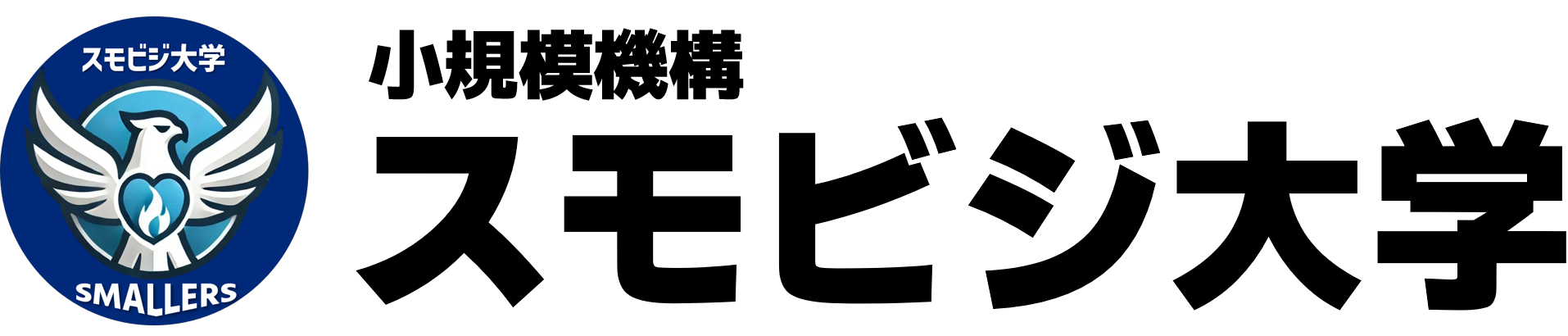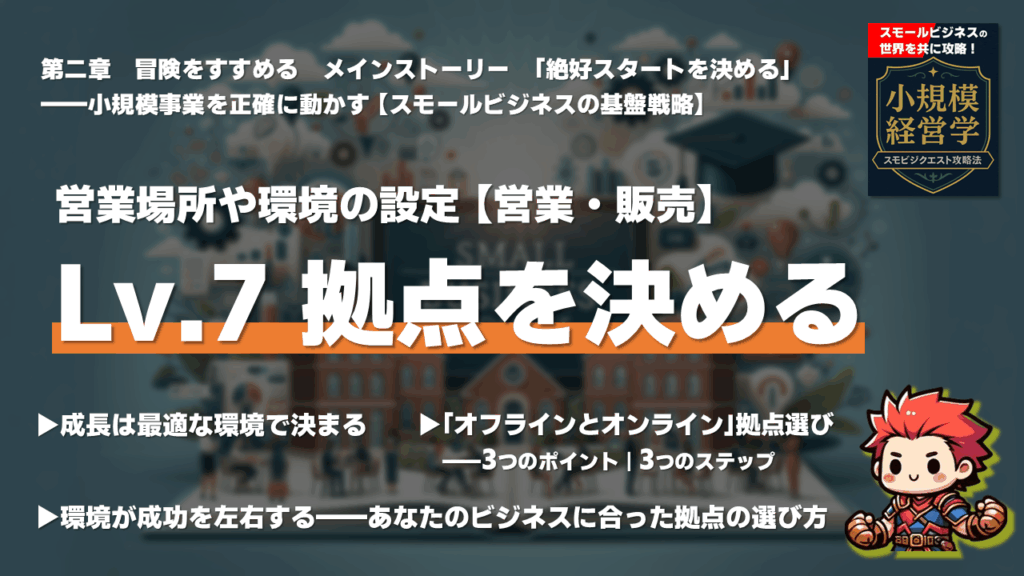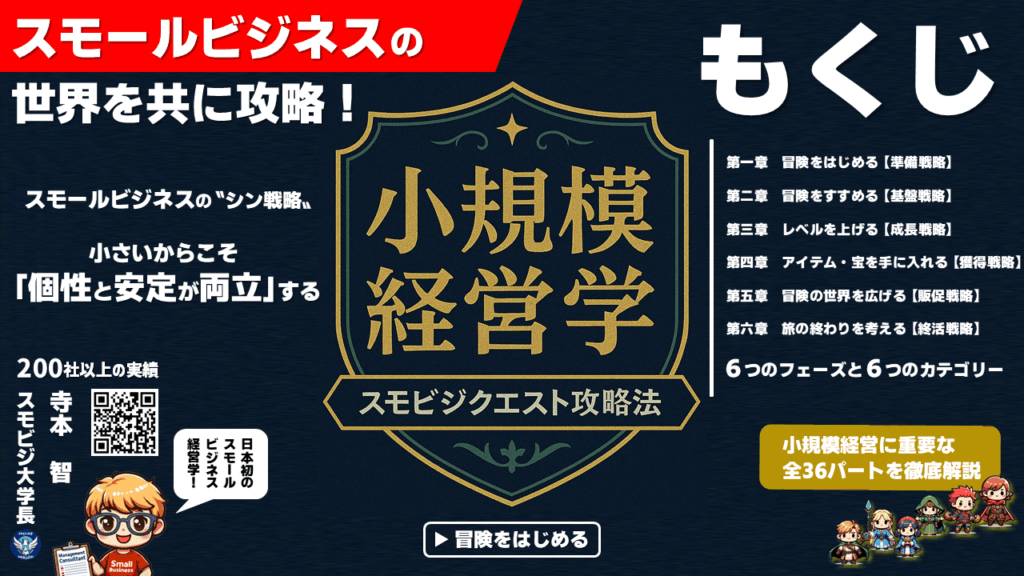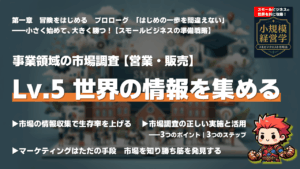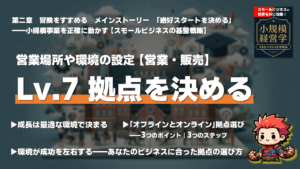Lv.6 冒険の計画書をつくる/事業計画書を作成する【経営・企画】|小規模経営学
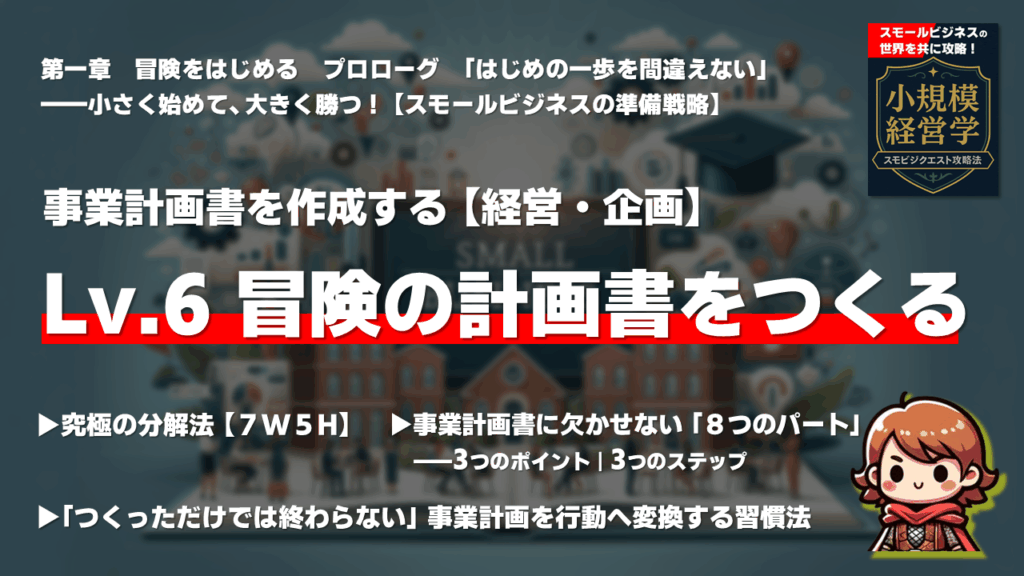
見出し
小規模だからこそ細部まで見える――究極の分解方法【7W5H】で考える
皆さんは、「事業計画書」と聞いて、どんな印象をお持ちでしょうか?
✓ おそらく…
「なんだか難しい…」
「書くのが面倒くさい…」
「融資や補助金のときにしか使わない書類でしょ?」
そんなふうに思っている方も、少なくないかもしれません。
確かに、事業計画書には「面倒くさい」「難しい」といった側面があるのも事実です。
しかし、良い事業には必ず、その基礎となる「設計図=事業計画書」が存在します。また、事業計画書は、融資や補助金・助成金を獲得するためだけのものではありません。
本来の目的は、お客様から大切なお金と時間をお預かりするプロセスを、あらかじめ可視化することにあります。
事業とは、常に変化し続けるもの。だからこそ、この「基礎図面」がないと、途中で方向を見失いやすくなります。とくに小規模経営の現場では、一人ひとりが日々、多岐にわたる業務を担っており、「計画を立てる時間」が後回しになってしまいがちです。
けれども、設計図のない家は完成しない。そんな家には住みたいと思えない――それと同じように、事業も「全体像を可視化する設計図」があってこそ、変化に応じた修正が可能になり、より良く、より強く、構築していけるのです。

う〜ん…事業計画って聞くだけで、プレッシャー感じちゃうのよね。ちゃんと書ける気がしない…

〝ちゃんと書こう〟としない意識も大事なんだよ。まずは自分の想いを言葉にしてみるだけでいいんだ
7W5H――解像度の高い「問い」で、詳細をつかむ
事業計画をつくるうえで、何よりも先に大切なのは――具体的な書き方ノウハウではなく、それを考えるあなた自身の視界がどれだけクリアになっているかです。
人は誰しも、準備運動なしに全速力では走れません。いきなり書き出すのではなく、まずは思考の筋肉をほぐすところから始めること。それが、優れたプラン設計の秘訣です。
ここで紹介する「7W5H」の視点は、事業計画を立体的に捉えるための最適なウォーミングアップになります。
この12の問いに沿って、あなたのビジネスを丁寧に分解していくことで、事業の解像度が上がり、現実に〝使える計画〟へと育っていくはずです。
【7W】と【5H】
- 誰が:Who → この事業をつくる〝あなた自身〝は、どんな人ですか?
- 誰に:Whom → その価値を本当に届けたい相手は、誰ですか?
- 何を:What → あなたが提供したいのは、どんな価値、どんな変化ですか?
- 何のために:Why → その事業の目的や使命は、どこにありますか?
- どんな質で:What quality → その価値をどんなクオリティで届けたいですか?
- いつ:When → 事業提供の最適なタイミングは、いつですか?
- どこで:Where → どんな場所・空間・拠点で届けたいですか?
- どんな方法で:How → どのような手段・方法・スタイルで提供しますか?
- いくらで:How much → 提供価格はどう設定しますか? どんな意味を込めますか?
- どれだけの量を:How many → 提供する数量は? 小さく始めるなら、どれだけが最適ですか?
- どれだけの期間:How long → いつからいつまで事業をしますか? 区切りと継続性のバランスは?
- どんなスピードで:How quickly → どれくらいのスピードで事業化をしますか?
この12の問いに対して一つひとつ丁寧に答えを導いてください。気づいたときには、あなたのビジネスが驚くほどクリアに見えているはずです。

プレナーって、なんでそんなに計画にこだわるの? やってみてから考えるのじゃダメなの?

もちろん、動きながら考えるのも大事。でもね、迷ったとき地図がないと元の道に戻れないんだ
シビレる事業計画を書こう!完成度の高い事業計画書に欠かせない「8つのパート」 3つのポイント
1)計画書は「あなたの想いをカタチ」にした〝存在の地図であり歩き方〟と捉える
事業計画書は、単なる「売上目標」や「利益計画」の表ではありません。そこにあるべきは、あなたという存在そのものが、なぜこの事業を始め、どう歩もうとしているのかを映し出す〝意思〟の輪郭です。
大企業の計画書と違い、小規模経営の計画書に求められるのは、「あなた自身の物語」を描き出すことにあります。
あなたが、なぜその商品を選び、なぜその価格で売り、なぜその場所を選んだのか。その一つひとつに、偶然ではない「選択の根」があるはずです。この根の部分を見えるカタチにしたのが事業計画書であり、唯一無二の「存在の地図」となるのです。

えっ? 事業計画って〝想い〟とか〝物語〟まで書くの? もっと数字の話だけかと思ってた〜

もちろん数字も大事。でもね、想いがなければ、計画の数字も達成しないんだ
見せかけの成長ではなく、本当の意味での納得と継続を生む地図。その地図には必ず道があります。だからこそ、「歩き方」も計画書に込めなければなりません。
それは、「いつ」「なにを」「どうやって」だけでなく、「自分にとって、どのような速度で」「どんな景色を見ながら」「誰と歩きたいか」——こうして、計画書は「売上計画」ではなく、「存在の証明」として輝き始めるのです。
2)〝描かないこと〟もまた、大切な計画――。
計画というと、「できるだけ細かく書くこと」が正しいと思われがちですが、実は、あえて「描かない」という決断も、立派な計画のひとつです。
それは、未来に余白を残すということ。
スモールビジネスは、予測不可能な変化にさらされるもの。計画の時点であまりに細部を固定してしまえば、かえって身動きがとれなくなることもあります。むしろ、「ここから先は、出会った人や現場の声を聞いてから決める」というスタンスが、小さな経営にはふさわしい場面も多いのです。
たとえば、新商品開発の詳細や、将来の事業拡張などは、あえて未記入にする。その代わり、「仮説と姿勢」だけを明記する。

でもさ、計画に書いてないことが起きたらどうするの? なんか不安で…

だからこそ、〝描かない〟っていう選択も大事なんだよ。全部書き込むより、変化に応じられる余白を持っておく。それが強い計画なんだ
✓ まだわからない未来を、きちんと〝わからない〟と書く
✓ しかし、どういう未来なら進みたいのか、その軸は描いておく
このバランス感覚がある計画書は、読み手にも信頼されます。それは、「完璧な正解」ではなく、「アップデート可能な意思」を伝えているからです。
3)伝えるだけの計画ではなく、「共鳴し、共振する計画」にする
事業計画書を「提出するもの」「審査されるもの」と考えると、つい一方通行な書き方になります。何より書いていておもしろくありません。宿題を無理やり提出しなければいけない、と思うようなものです。
小規模経営において、最もパワーを持つ事業計画書は、読み手の心に〝共鳴〟を起こすものです。
あなたの計画を読んだとき、そこに関わりたくなる。応援したくなる。いっしょに夢を見たくなる。それは、数字や言葉が整っているからではなく、その計画が「人間らしい感情」をまとっているからです。
✓ たとえば…
- あなたの原体験からにじみ出るストーリー
- 苦手なことを正直に記し、それでも進もうとする決意
- 顧客や地域への敬意と愛着
そうしたものが丁寧に記されている計画書は、読み手の中で〝共振〟を起こします。読み終えたあと、思わず「この人の成功を見たい」と感じさせる力があるのです。
事業計画書は、金融機関や補助金審査官に届ける「説明資料」ではなく、未来の仲間に出会うための「共鳴装置」といっても過言ではありません。そしてそれは、やがて人を動かし、確かな物語を生み出していきます。
3つのステップ
完成度の高い事業計画書には、構造と説得力があります。ただ夢を語るのではなく、実現可能な道筋を示すことが重要です。ここでは、その「8つのパート」を的確に組み立てるための3つのステップを解説します。
① 欠かせない「8つのパート」を理解する
まずは、完成度の高い事業計画書に欠かせない「8つのパート」をしっかりとおさえておきましょう。
計画書は、あなたの想いや構想を伝えるための設計図であると同時に、相手に「信頼」や「納得感」を届けるための地図でもあります。その詳細をしっかりと描き出すために必要なのが、次の8つのパートです。
この8つの項目をおさえておくだけで、あなたの事業の全体像は明確になり、誰が読んでも「どんな事業なのか」「なぜいまこれをやるのか」が伝わる構成になっています。
1.企業概要と経営方針:あなた(企業)は誰か?
あなたは何者で、なぜこの事業を考えたのか?――自己紹介と意志を語るパートです。経験や背景動機、解決したい社会課題などを交え、「なぜこの事業に自分が取り組むのか」を明示します。「だから、こう決めた」――。
2.事業タイトル・事業内容::何のために、何をしますか?
この事業は、何を、どう届けるのか? どう売るのか?――事業の本質をひと言で伝えるタイトルと、簡潔な内容の説明が求められます。
3.ビジネスモデル図:わかりやすく図解で
文章だけでは伝えきれない、価値の流れを「図解」で表現します。提供価値・顧客接点・収益構造などを視覚的に見せることで、直感的に理解を促します。
4.事業の特徴・強み:何が売りですか?
あなたの事業が「他と違う」理由を明確にします。「新規性・独創性・優位性」の3点を中心に、選ばれる理由を示しましょう。
5.マーケティング分析:ちゃんと調べていますか?
誰に届けたいのか?――ターゲット市場や顧客層、競合との違いを具体的なデータや現場感覚を交えて示します。とくに重要なのは、「この事業がどの市場で、どのように機能するのか」を明確にすることです。
6.事業の目標(効果)と見通し:どれだけ儲かりますか?
どれだけの成果を、どう目指すのか?――売上や利益の見込みだけでなく、事業が持つ社会的なインパクトや、地域とのつながりについても触れることで、計画全体がよりリアルなものになります。
7.チーム体制・スケジュール:この事業をどう進めますか?
目標を達成するためには、実行力が不可欠です。各メンバーがどのような役割を果たすのか、プロジェクトがどのようなタイムラインで進行するのかを明確に記載することで、実現可能性の信頼度が上がります。
8.資金使途・調達方法:何に、いくらお金を使いますか?
最後に、資金の使い道とその調達方法について具体的に記載します。「どの部分にいくら必要なのか」を明確に示します。資金計画を明確にすることで、経営の透明性を担保し、支援者の信頼を得ることができます。
この8つのパートは、それぞれが「点」ではなく、「線」でつながっています。
あなたのビジネスが「なぜはじまり、どこを目指し、どう進んでいくのか」を、読み手が自然に理解できるように構成されているのです。
事業計画とは、頭の中にあるイメージを他者と共有できる言語にすること。この8つをしっかりおさえることで、「伝える」だけでなく、「伝わる」計画へ変化してきます。

うーん、なんだかパートが多くて、覚えきれる気が

全部を丸暗記しなくても大丈夫。〝なぜ・何のために・誰に・どうやって〟って流れで考えたら、自然と8つのパートに沿ってくるよ
② 流れを描き、全体像を俯瞰する――図解とビジネスモデル
事業計画の質は、「全体像の見せ方」によっても大きく変わります。どんなに優れた計画も、読み手にとってわかりにくければ、魅力は伝わりません。だからこそ、「全体像の流れ」を意識して、ビジネスを〝絵〟で伝える力を持ちましょう。
とくに有効なのが、「ビジネスモデル図」や「プロセス図」の活用です。あなたの事業が、どこから価値を生み、どのようにお客様へ届き、どうやって収益化するのか――その一連の流れを図で可視化することで、直感的に理解が深まります。
また、図解を通してはじめて、自分自身が「抜けていたポイント」や「複雑になりすぎた部分」に気づくことも多いのです。計画は、俯瞰することでシンプルになります。そしてそのシンプルさは、他者に伝わる大きな武器となります。
③「お金・スケジュール・チーム」の管理を綿密に計画する
最後のステップは、現実に動かすための「管理」の設計です。どんなに想いのある事業も、時間とお金と人のリソースがなければ実現しません。この3つは、小規模経営においてとくに「慎重かつ柔軟」に扱うべき大切な要素です。
✓ どこにどれだけお金を使うのか?
✓ どのタイミングで何を実行するのか? いつまでに終わるのか?
✓ 誰と協力し、どのような役割で進めるのか?
これらの項目は、計画の信頼性を高めるだけでなく、あなた自身の「動く覚悟」を確認するものでもあります。
お金・スケジュール・チーム――この3つのリアリティが計画にしっかり描かれていることで、読み手は「実現できそうだ」と感じ、行動の支援者が増えていきます。

計画って想いやビジョンを、リアルにしていく作業なのね

そうだね。情熱があるからこそ、お金と時間と人の〝現実〟も、きちんと見ておくんだよ
この3ステップを経ることで、事業計画は「自分のためのメモ」から、「他者を巻き込むための設計図」へと進化していきます。
それは、あなたの想いが、誰かの心に届く瞬間をつくる「準備」でもあるのです。
「つくっただけでは終わらない」事業計画を行動へ変換する習慣法
立派な事業計画をつくったのに、現実はなかなか動き出さない――そんな経験はありませんか?
それは、あなたの情熱や努力が足りないからではありません。計画と行動のあいだには、〝思考と実践〟をつなぐ「習慣」という橋が必要なのです。
「行動しない前提」で準備しておく
人は誰しも、未来の自分に期待しすぎてしまうものです。しかし、スモールビジネスでは、日々の業務が想定以上に重なり、計画どおりに行動できないことが日常です。だからこそ、「やらない前提」で準備しておくことが、大きな成果を生みます。
✓ たとえば…
- 行動を細分化して、15分でできる単位にまで分けておく
- 「毎週〇曜日に、30分だけ取り組む」と習慣に組み込む
- できなかった日のための「ゆるい代替プラン」を準備しておく
具体的に、「SNSを週に3回更新する」ことを計画していた場合、「書けなかった日は以前の投稿をリライトする」といったような〝逃げ道〟を用意しておくことで、継続への心理的ハードルが下がります。
「ノート」に書き出して、見える化をする
思考を整理し、行動に変えるうえで最も効果的なのが、〝ノートの力〟です。
計画や進捗をデジタルで管理する方法もありますが、手書きによって頭と手を連動させる行為は、記憶の定着・思考の整理・直感の発見において圧倒的に優れています。
ハーバード大学の研究でも、「手書きによるメモは、情報の構造的理解と行動転換を促す」というデータがあり、複雑なアイデアを分解しながら思考を深めるのに効果的とされています。
ビジネス手帳を活用し、メモとスケジュールを一括管理することは、最適な習慣法といえるでしょう。
「事業計画書そのもの」に書き込むという習慣
ノートを使って思考整理し、進捗管理をすることに加えて、もうひとつ大切なのが、「事業計画書そのものに書き加えていく」という発想です。
スモールビジネスにおいて、事業計画書は「完成品」ではなく「進行形の設計図」です。だからこそ、実際の行動や気づきを、そのまま書き加えていくことが可能なのです。
たとえば、印刷した計画書に余白をつくって、進捗のチェックや反省点を書き込む。あるいは、PDFやノートアプリなどに直接メモを加える——こうした〝計画と行動をひとつの場に置く〟ことが、実践力を高めるカギになります。
✓ 事業開始から3か月で、予定とのギャップが見えてきた
✓ 新たな顧客層に出会い、届けたい言葉が変わった
✓ チーム内で認識にズレが生まれていた
こうした変化や気づきは、最初の計画書には書かれていなかった「リアルな声」です。だからこそ、その声を計画書に反映し続けることで、事業計画書は〝書いたときよりも、ずっと優れた設計図〟へと育っていくのです。
「計画は、書いて終わりではない」――行動に変換してこそ価値があるという本質を決して忘れてはいけません。
あなたの手で日々描き続ける限り、事業計画書は、いつでも〝次の一歩〟を教えてくれる心強い味方になります。
まとめ――体験事例と共に 本章の旅を振り返る
私たちはこの第一章で、「はじめの一歩を間違えない」――小さく始めて、大きく勝つ!【スモールビジネスの準備戦略】という、小規模経営ならではの本質を探ってきました。
キャラクターの設計、理想の世界の描写、オリジナルスキルの装備、資金調達、そして「計画」を「共鳴装置」として捉える視点――。
どれも、小さな経営だからこそ見える細部を、丁寧にすくい上げるものでした。この章で伝えた考え方がどのように実際の現場で力を発揮したのか、ひとつの事例を紹介します。
――ある製造業の現場でのこと。繊維関係の家業を継いだ、40代のNさん。
彼は、決して「起業家」ではありませんでした。もともと父親の跡を継ぐかたちで、事業を引き受けた――ただ、それだけのきっかけだったのです。
「自分のビジョンなんて、なかったです。正直、会社をどうしたいかなんて、考えたこともなかった」そう彼は語っていました。
経理も資金繰りもすべてひとりでこなし、当然ながら計画も立てず、日々の対応に追われるばかり。気がつけば、事業はいつの間にか「続けるだけ」で精一杯になっていたのです。
そんな中、コロナ禍が襲いかかり、売上は大きく落ち込みました。主要顧客が倒産し、資金繰りは限界。
「このままでは会社が終わってしまう――」
はじめて、彼の中に〝危機感〟ではなく〝覚悟〟が芽生えた瞬間でした。補助金申請のために必要となった「事業計画書」。そこから、彼は本気で仕事に向き合い始めたのです。何を書けばいいかわからない——けれど、何も書けないということは、何も考えてこなかった証拠だと気づきました。
そこで、この章でも紹介した7W5Hや8つのパートに沿って、自分自身に問いを立てていきました。
✓ 自分は、何者なのか?
✓ 誰に、何を届けたいのか?
✓ どうやって売り、どう成長したいのか?
✓ いまの自分に欠けている視点は、どこにあるのか?
こうした問いと答えを、毎晩ノートに書き出しては眺め、少しずつ修正していく日々。ときに社内の仲間とも話しながら、「いままでの延長線」ではなく、「これから」の道を、自分の手で設計していったのです。
その結果、1年後――。
彼の事業は前年比175%の成長を達成しました。受け身だった姿勢が、主体的な提案へと変わり、取引先との関係も再構築。スタッフのモチベーションも上がり、社内の雰囲気も活気に満ちてきました。
Nさんは、こう語ってくれました。
「計画って、事業のために書くものだと思ってた。でも本当は、自分の人生を取り戻すためのものだったんですね」
――このひと言に、小規模経営の本質が、すべて詰まっているように思います。
〝小さな事業〟だからこそ、大きな方向転換もできる。それを体現した貴重な事例だったと、いまでも感じています。
そして、あの日ノートに向き合ったNさんのように、私たちもまた、「なぜこの道を歩むのか」を何度でも問い直すことができる――その確かさこそが、小さな経営の静かな力なのです。
旅便り:やる気スイッチなんてない――本当に押すべきは、「やる気ブレーカー」
「やる気が出ないんです…」
そんな声を、何度も聞いてきました。かつて私自身も、同じように「やる気スイッチ」を探して、右往左往していた時期がありました。
けれど――本当に必要だったのは、スイッチなんかじゃなかったのです。
たとえば、水泳がすぐに上達するスイッチなんてありません。ピアノが急に上手くなるスイッチも、もちろんありません。
それにもかかわらず、ことビジネスや人生の転機においてだけは、「スイッチさえ押せば変われる」と思い込んでしまう。確かに、きっかけになる行動や言葉、心を突き動かす出会いはある。それらは一瞬、「スイッチ」のように感じられます。
しかし、それはあくまでも点火剤に過ぎません。スイッチのように、軽く押せばすぐに光り、また簡単にOFFになるものでは、何も継続しません。
むしろ本当に押すべきは、もっと重くて深いもの。そう、それは――「やる気ブレーカー」です。
ブレーカーを押すには、ちょっと力がいります。軽い気持ちでは動かない。少しの勇気と、少しの力。でも、一度〝カチッ〟と押し込めば——めったに切れることのない、内なるエネルギー源にスイッチが入る。
表面がパチパチと燃える「赤い炎」ではありません。一見目立たないけれど、しんしんと燃え続ける「青い炎」。
いや、それよりも静かでたしかな「焚き火の種火」。風に煽られても消えず、水に濡れてもじわっと立ち上がるような、あの小さな火です。
この「やる気ブレーカー」は、他人の目や評価には反応しません。けれど、自分の中の「本気」には応えるもの。誰かに見せるための情熱じゃなく、自分にだけわかる、静かで強い決意。それが、やる気ブレーカーなんです。
もしいま、やる気が出ないと感じているなら、それは「スイッチが押せない」のではなく、まだ「ブレーカーが入っていない」だけかもしれません。
スモールビジネスの旅は、毎日が予想外の連続です。やる気スイッチではなく、やる気ブレーカーを押すこと。そして、自分だけが知るその火種を、絶やさないこと。
あなたの中にある「静かな炎」が、これからを照らし続けますように。この旅が、少しでもその灯になれたらと願っています。
――ではまた、次の旅便りで。
それでは、次のレベルへご案内します。
↓ もくじはこちらから ↓
寺本 智(てらもと さとし)
小規模経営学者│スモビジ大学長│小さいからこそ「個性と安定が両立」する『小規模経営学』を体系化│スモールビジネス分野で、教育・コンサルティング・小説を執筆│スモールビジネスコンサルタントとして、10年以上にわたり、従業員0人から20人まで(商業・サービス業は基本5人以下)の小規模企業を200社以上サポート。
活動理念は、『小さな事業を大きな主役へ』。一人ひとりが持つ個性と、経済的な安定。この2つが両立する――そんな〝小さな経営の在り方〟と、スモールビジネスを200社以上サポートした実体験から得た、「小さくても大きな成果を導くことができる」独自の文法を、小規模事業の【6つのフェーズ】と【6つのカテゴリー】に合わせて体系化。
ビジョンは、小さな事業が大きな主役となり、『個性と安定が、両立する社会』――「一億総スモールビジネス」。
▶ スモビジ大学のプログラム

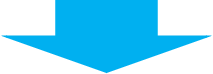
↓ 画像をクリック ↓