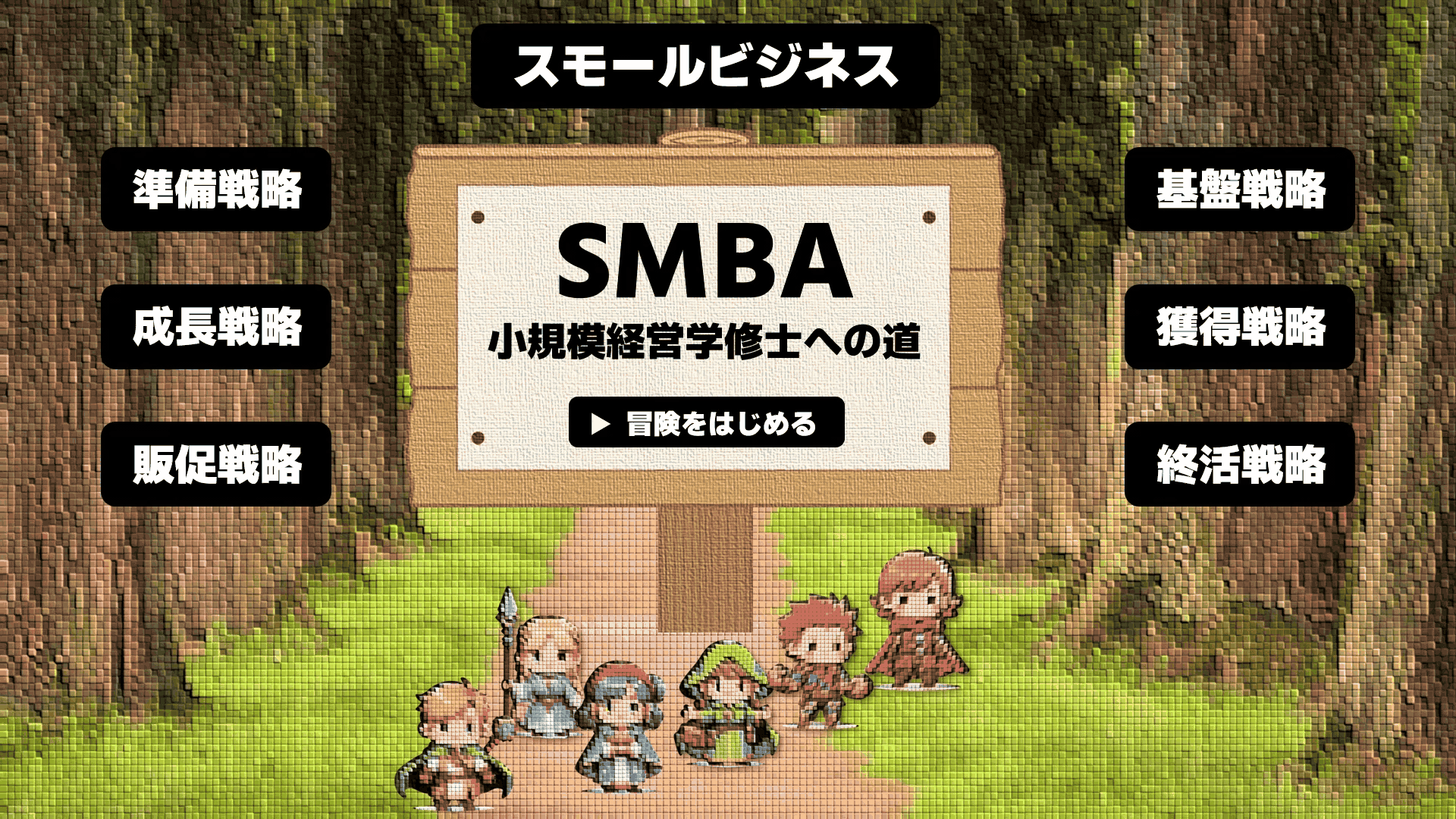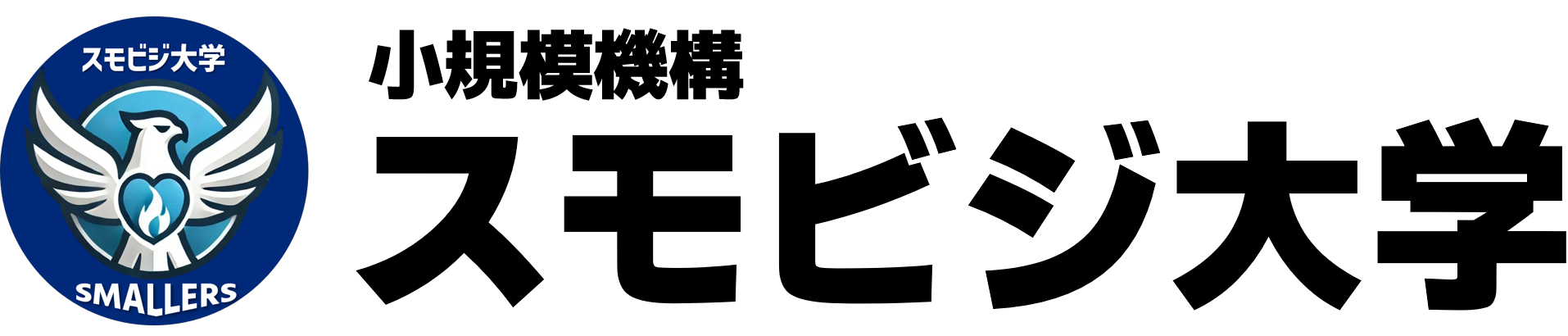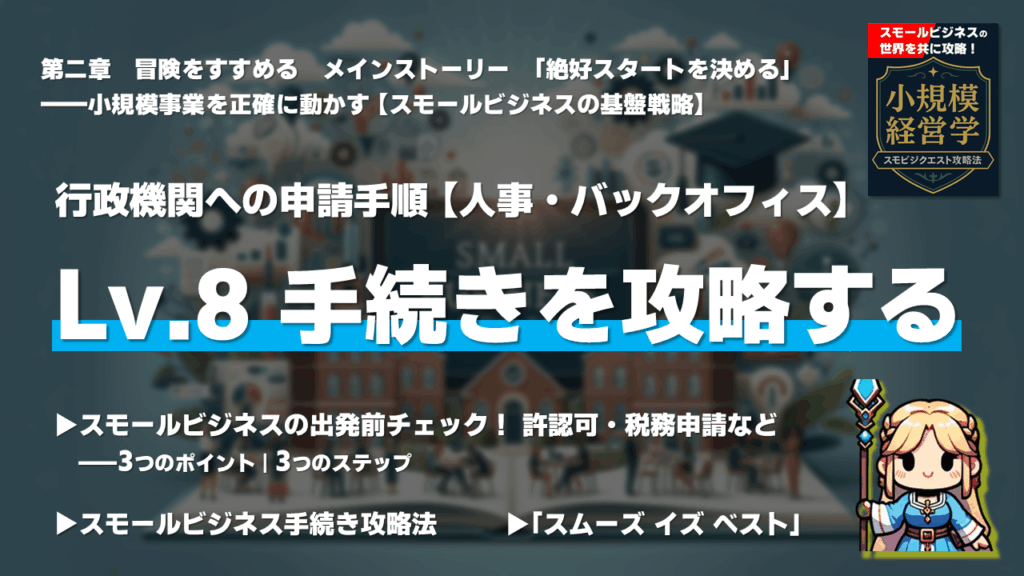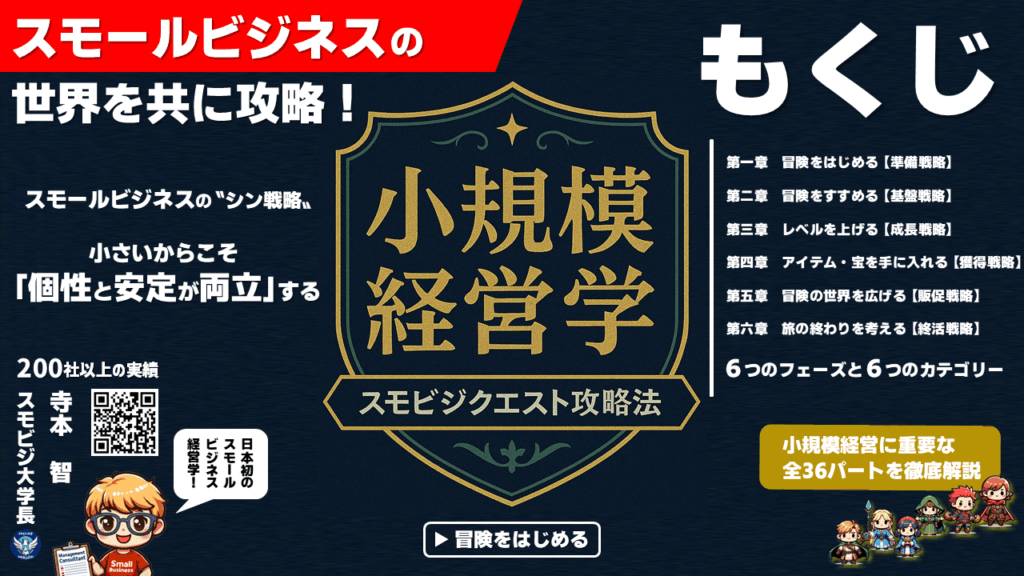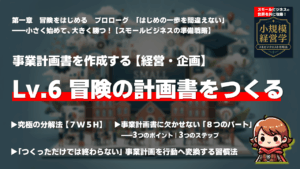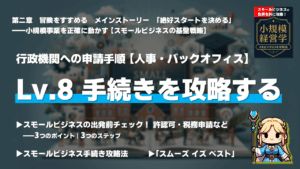Lv.7 拠点を決める/営業場所や環境の設定【営業・販売】|小規模経営学
第二章 冒険をすすめる メインストーリー
「絶好スタートを決める」――小規模事業を正確に動かす【スモールビジネスの基盤戦略】
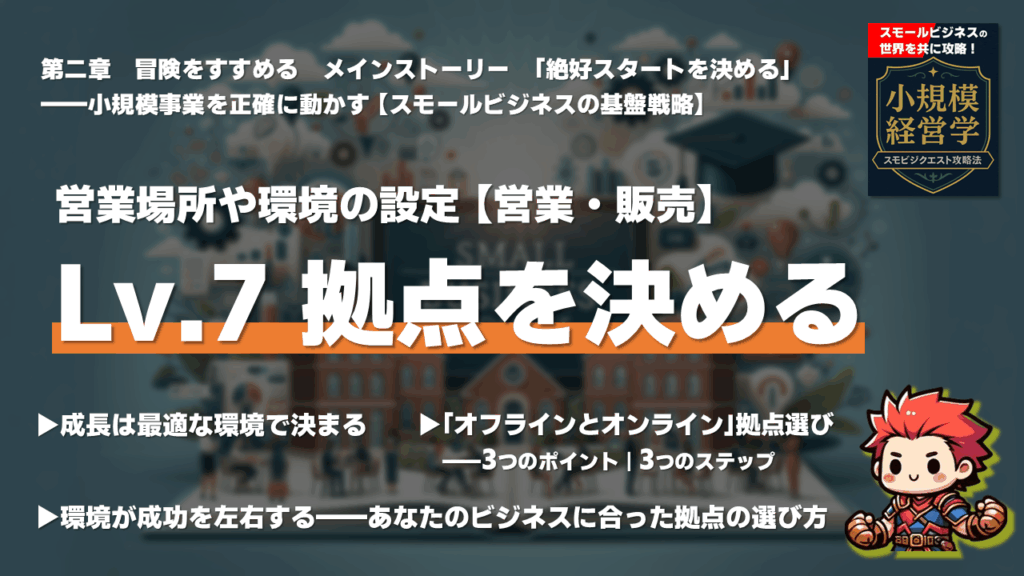
見出し
スモールビジネスの成長は拠点で決まる――最適な環境を選ぶ戦略
スモールビジネスを動かすうえで、見落とされがちですが、極めて重要な要素があります。それは、「拠点をどこに構えるか」ということです。
この選択は、事業の命運を分ける可能性があります。どれだけ良い商品やサービスがあっても、その価値が「届かない場所」にいたのでは、前に進みません。拠点選びは、ただの「場所選びではない」のです。
✓ 誰に出会えるか
✓ どんな環境に身を置くか
✓ 日々、何に影響されるか
それらをすべて含んだ、「行動と思考の舞台」そのものにもなり得るからです。
小さな経営にふさわしい拠点の選び方
スモールビジネスの拠点戦略は、大企業のように資本力で勝負するわけにはいかない――だからこそ、次のような点をおさえる必要があります。
- 最短で事業に貢献する場所か?
- モチベーションが自然と高まる環境か?
- 変化にすばやく対応できる柔軟性があるか?
この3つは、小規模事業の拠点選びをするうえで、とても重要な視点です。
拠点が変わると、行動が変わる
たとえば、自宅で作業していた人が、思い切ってコワーキングに通い始めたとします。出会う人が変わり、言葉が変わり、自然と行動も変わっていく――それは、拠点が〝自分を変える装置〟になったという意味でもあります。
スモールビジネスでは、経営者自身の在り方や行動が成果を左右します。だからこそ、「どこで働くか」は、「どう働くか」「どう変わるか」と直結しているのです。

マーケン。どうして場所選びがそんなに大事なの?

拠点ってね、自分がいちばん長くいる〝営業ツール〟なんだよ。どこにいるかで、誰と出会い、何に触れるかですべて変わるからね
地元か?都市か?という問いに終止符を
「地元でやるべきか? 都市に出るべきか?」―― この問いに、唯一の正解はありません。
大切なのは、あなたの価値が、最も伝わる場所を選ぶこと。地元が合わないなら、無理にとどまる必要はないですし、都市に出ても、活かせないなら本末転倒です。
「あなたの本質と価値が最も伝わる場所は、どこか?」その視点を常に持つことが重要です。
拠点はなにも、リアルなオフラインの世界だけではありません。オンラインというインターネット環境でビジネスが成立する時代です。地方都市に拠点を構えていたとしても、ネットのプラットフォームを活用することで、あなたのビジネス販路は無限に広がります。詳しくは、✓【Lv.23 アプリ・プラットフォームを利用する】で、解説します。
成長する事業は、拠点の設定や見直すことから
ステージが変われば、拠点も変える。顧客が変われば、動く場所も変わる。自身の集中力が下がってきたら、環境も見直す――成長を続けるスモールビジネスは、「拠点の設計と再構築」が習慣になっています。一度決めた場所に固執せず、「いまの自分にとって最適か?」を問い直す。それが、未来を開く良質な経営者の判断力です。
「オフラインとオンライン」拠点選びの選択肢を整理する 3つのポイント
1)拠点には「2つの領域」がある――物理空間と情報空間を使いこなす
拠点とは、単に「お店がある場所」「オフィスの住所」といった物理的な立地だけを指すものではありません。現代のスモールビジネスでは、「物理空間(オフライン)」と「情報空間(オンライン)」の両方が、拠点として機能します。
たとえば、ある小さなパン屋さんが、リアルの店頭販売に加えて、Instagramを通じて毎日の焼き上がり情報を発信していたとします。そのSNS上のアカウントもまた、「お客さまと出会う拠点」なのです。
✓ 自宅兼オフィスで活動するフリーランス
✓ 小さなサロンとLINE公式アカウントを併用する美容師
✓ 地方に住みながら、Zoomとnoteで全国とつながる講師業
こうした働き方において、オンライン拠点は単なる「ツール」ではなく、「出会いと価値提供の場」そのものとなっています。
つまり、現代の拠点戦略とは――「場所を決めること」ではなく、「空間を設計すること」なのです。

オフラインとオンラインって、結局どっちが正解なの?

正解は〝どっちも活かす〟だね。最適な空間選びをすることが大事なんだ
2)オフラインは「信頼性と体験価値」/オンラインは「拡張性と継続性」
オフラインとオンライン、それぞれの拠点には明確なメリットと特徴があります。小規模経営だからこそ、その違いを正しく理解し、自分の事業に合わせた使い方が求められます。
オフライン(リアル)の拠点のメリット
- 「空気感」「対面の安心感」「その場の温度」など、信頼性と体験価値を提供できる
- 一度の出会いが深い関係性につながりやすい
- 地元密着型のサービスや、高価格帯の信頼ビジネスに向いている
オンライン(情報空間)の拠点メリット
- 時間や場所に縛られず、拡張性と継続性がある
- コンテンツを積み重ねて、資産のように機能する
- SNS、note、YouTube、Zoom、ECサイトなど、さまざまな形で構築できる
どちらかが優れている、という話ではありません。重要なのは、「誰に、どんな価値を、どんな方法で届けるのか」という観点から、それぞれの特性を活かすことです。
3)選ぶ時代から、掛け合わせる時代へ――ミックス拠点のすすめ
「オンラインか? オフラインか?」という二択で考える時代は、もう終わりです。いま求められるのは、「自分に最適なバランスで、両者を掛け合わせる」設計力です。
✓ たとえば…
- リアルで商品を体験してもらい、オンラインでフォローアップや再購入につなげる
- オンラインで信頼を育て、リアルのイベントや個別対応で深く関わる
- ネット上の集客から、地元の実店舗へ送客する
こうした「ミックス型」の拠点設計は、スモールビジネスだからこそ柔軟に取り入れられます。しかも、拠点は変化して良いのです。
環境や顧客の変化にあわせて、主戦場をオンラインに移すこともあれば、リアルの拠点を持つことで信頼と安心を補強することもあるでしょう。大切なのは、「いまのあなたに合った拠点設計とは何か?」を問い直し続け、再設定を常に図ることではないでしょうか。

えっ? でもオンラインって難しそうだし…はじめから両方は無理かも

自分の得意なほうから始めて、あとから掛け合わせればいいんだ。拠点は〝増築〟していいんだからさ
3つのステップ
ビジネスの拠点をどこに置くかは、成果を左右する大きな要因です。店舗かWebか、あるいはその両方か。自分のビジネスにとってベストな拠点戦略を選ぶための3つのステップをお伝えします。
①「価値の届く場所」を見極めるため、「どこで届けるか」を言語化する
スモールビジネスの拠点戦略で最初に考えるべきは、「あなたの価値が、どこで響くのか?」という問いです。それは、偶然ではなく、意識的に選び取るべき設計です。
たとえば、あなたの商品は「手に取って体験してもらう」ことで魅力が伝わるのか? それとも、「言葉で深く語る」ことで共感を得るのか? その特性によって、届けるべき場所はまったく異なってきます。
ポイントは、「届け方」を考える前に、「どこで届けるか」を言語化することです。「この場所で、この人に、この価値を伝えたい」と明確に言葉にしてみる。たったそれだけで、拠点の選び方は自然と見えてきます。
✓ 駅前の路面店か、裏通りの小さなギャラリーか?
✓ インスタでファンとつながるのか、リアルな体験で心をつかむのか?
✓ 地元密着なのか、全国へ広げていくのか?
一つひとつを「感覚」ではなく「言語」で捉えること。それが、自分にとって本当に意味のある拠点設計のスタート地点になります。

この商品、どこで売ったら〝ウケ〟がいいんだろうって、みんな感覚で決めがちなんだよね

うんうん。でも、『言葉にしてから動く』って聞くと、すごく納得する~
②「自分らしく動ける拠点」を選ぶ――成果よりもまず、続けられる設計をする
どれだけ戦略的に優れた拠点でも、「気が重くて、足が向かない」場所では意味がありません。
スモールビジネスにおいて大切なのは、戦略よりも先に「その場所が自分にとって、自然体でいられるかどうか」。つまり、自分らしく動けるかどうかです。
✓ 毎朝ワクワクして鍵を開けられる場所か?
✓ 顔を合わせたい人がそこにいるか?
✓ 自分の言葉やリズムが、無理なく出せる空間か?
そんな「感情のコンディション」こそが、小さな事業では成果を左右します。成果は、継続からしか生まれません。だからこそ、「売れるかどうか」ではなく、「続けられるかどうか」の視点で拠点を設定する――それが、スモールビジネスにおける〝最適解〟なのです。

売れそうな場所って聞くと、どうしても人が多いところに惹かれちゃう…

うん。でも〝売れるよりも、続けられるか〟が大事なんだね
③ 拠点は「仮説」決定で、試しながら再設計する前提で動く
拠点選びは、一度決めたら固定されるものではありません。むしろ、環境や自分自身の変化に合わせて、「仮説→検証→修正」のサイクルを回すことが重要です。
たとえば、開業当初は自宅兼オフィスでスタートした人が、「集中できない」「孤独感がある」と気づき、数か月後にコワーキングに拠点を移す。あるいは、オンラインで全国に商品を売っていた人が、「やっぱり地元の声を大事にしたい」と思い直し、ローカルイベントに出店する——こうした変化は、すべて〝正解〟です。スモールビジネスの拠点戦略は、「最初からベストを決める」のではなく、「仮説でいいから一歩を踏み出し、そこから再設計していく」ものなのです。
✓ 迷ったらまず、小さく試してみる
✓ 数か月に一度、振り返りの時間をとる
✓ 合わなければ、変えることを恐れない
この〝仮説思考〟と〝再設計習慣〟がある限り、あなたの拠点は常に「最適」に進化し続けます。
拠点とは、「物理的な場所」以上に、「自分の価値を、誰に、どこで、どう届けるか」を具体化するステージそのものです。「迷いながらでいい」。まずは動いてみて、その場所に自分の足跡を刻みながら、その場所を〝あなたの物語が生まれる拠点〟へと変えていきましょう。

なんだか、最初から完璧を目指しちゃうんだよね…

完璧なんて、あとからでいいさ。〝仮拠点〟くらいの気軽さでいこう!
環境が成功を左右する――あなたのビジネスに合った拠点の選び方
スモールビジネスにおける「拠点選び」は、単なる住所や立地の話ではありません。それは、日々の思考を整え、行動の質を引き上げ、未来への姿勢さえ変える――そんな「環境設計」の話でもあります。
静かな場所か、にぎやかな場所か。人が多い場所か、ひとりで集中できる場所か。自然の近くか、デジタルに強い街中か。その環境が、どんなふうに自分を動かしてくれるか。これらの要素はすべて、あなたのビジネスにとっての「生産性」「創造性」「持続性」に深く影響します。
つまり、「成功するかどうか」は、あなた自身の能力よりも、環境設計の巧拙に左右される場面が意外と多いのです。
環境設計は、「成果の出やすさ」を操作する技術
ある実験では、「静かな図書館」と「ざわざわしたカフェ」それぞれで同じ課題を解かせた結果、人によって集中度や創造性が大きく異なったというデータがあります。
「どこでやるかは、何をやるかと同じくらい」重要だということです。成果とは能力の結果ではなく、環境との相性の産物でもある――この視点は、スモールビジネスにとって、非常に大切です。
あなたのビジネスに合った環境とは何か?
ここでもう一度、自分のビジネスに必要な「環境の条件」を考えていきましょう。
- 売上につながる活動が増える場所か?
- お客様との信頼構築がしやすい空間か?
- 自分が創造的・前向きでいられるか?
こういった問いを考えることで、あなたに適した環境設定が可能になります。
成果を上げている人の多くが「環境」を味方につけている――。
成功している小規模事業者の多くは、拠点をただの住所としてではなく、「成果の出る仕組み」として使いこなしています。
拠点=拠る点(よりどころ)を複数持ち、それぞれに役割を与えて使い分ける。そんな柔軟な設計力が、スモールビジネスの成長には欠かせません。
拠点は、思考と行動だけでなく「補給」の場にもなります。
ビジネスを続けるということは、エネルギーを使い続けることでもあります。だからこそ、ときには立ち止まり、情報や視点、そして言葉や勇気を補給する場所が必要です。
✓ たとえば…
- 商工会議所や地域活性化センターなどで、制度のアドバイスや新しい支援情報を得る
- 同業者や異業種の仲間とミーティングすることで、自分では思いつかなかった視点をもらう
- 勉強会や交流イベントに参加し、モチベーションをチャージする
こうした「補給のための環境」を、あらかじめ拠点設計に組み込んでおく。それは、孤独になりがちなスモールビジネスにおいて、ありがたい〝防御力〟になります。
「仕事をするための場所」だけでなく、「学ぶ」「振り返る」「支え合う」ための場所も、拠点の一部だと捉えること。それが、あなたのビジネスを、さらにしなやかに、持続的に支えてくれるはずです。
良い環境とは、あなたの背中を、そっと前に押してくれるものです。最適な拠点を探すことは、自分の未来にふさわしい「日常の舞台」を選ぶことでもあります。環境が整えば、仕事は自然と前に進みます。迷ったときは、こう問い直してみてください。
「私にとってどんな場所が、未来に向かって自然と動き出せる環境か?」その答えが明確にイメージできるなら、そこはあなたにとって、きっと「正しい拠点」としてふさわしいでしょう。
それでは、次のレベルへご案内します。
↓ もくじはこちらから ↓
寺本 智(てらもと さとし)
小規模経営学者│スモビジ大学長│小さいからこそ「個性と安定が両立」する『小規模経営学』を体系化│スモールビジネス分野で、教育・コンサルティング・小説を執筆│スモールビジネスコンサルタントとして、10年以上にわたり、従業員0人から20人まで(商業・サービス業は基本5人以下)の小規模企業を200社以上サポート。
活動理念は、『小さな事業を大きな主役へ』。一人ひとりが持つ個性と、経済的な安定。この2つが両立する――そんな〝小さな経営の在り方〟と、スモールビジネスを200社以上サポートした実体験から得た、「小さくても大きな成果を導くことができる」独自の文法を、小規模事業の【6つのフェーズ】と【6つのカテゴリー】に合わせて体系化。
ビジョンは、小さな事業が大きな主役となり、『個性と安定が、両立する社会』――「一億総スモールビジネス」。
▶ スモビジ大学のプログラム

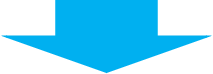
↓ 画像をクリック ↓