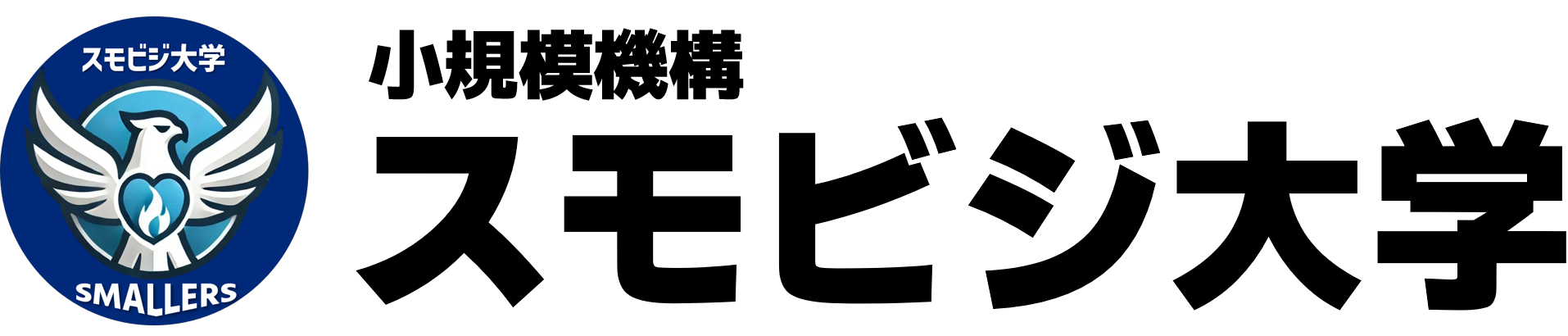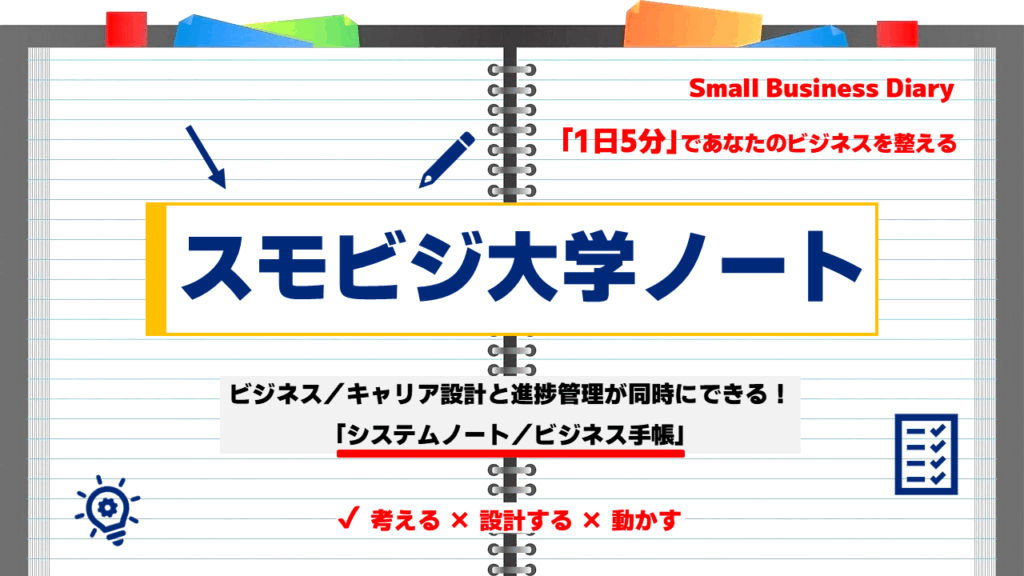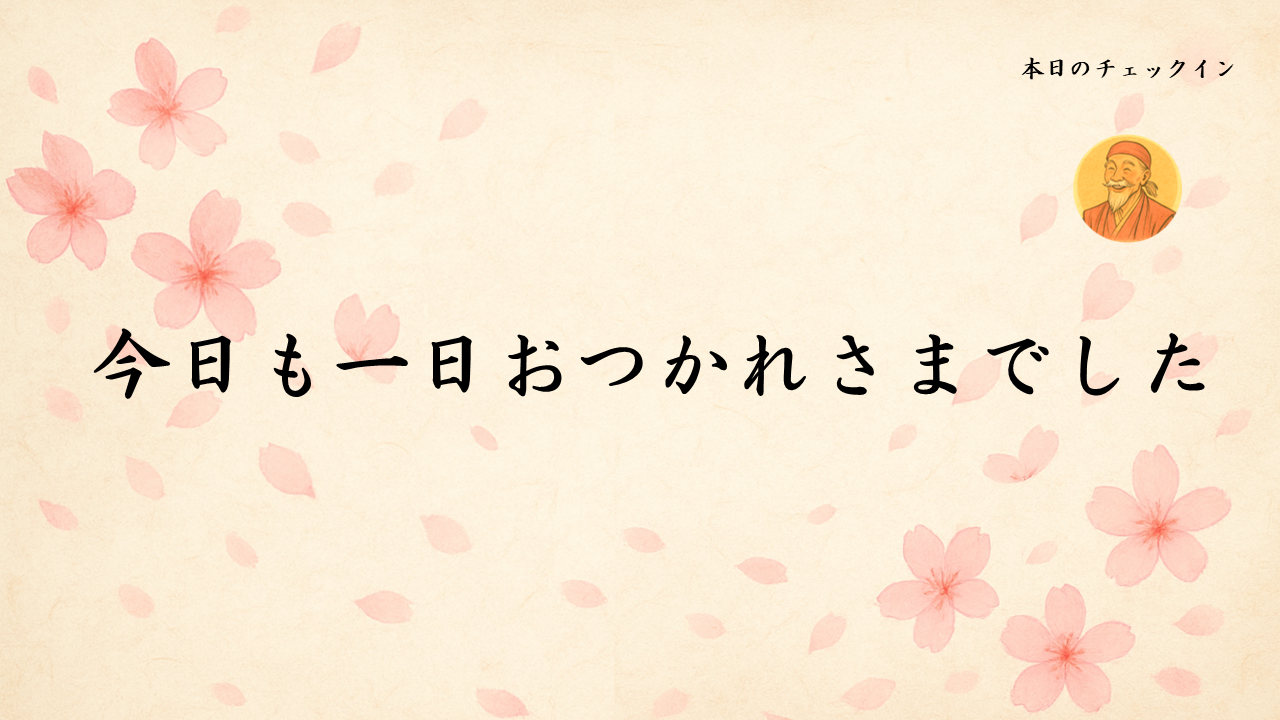
🌸花咲亭好々爺(はなさきてい こうこうや)
「元禄笑福指南役」👉 生没年:元禄三年(1690年)生まれ/没年不詳(※未だどこかで語り歩いているとの噂あり。目撃情報も多数寄せられている)
👉 出身地:江戸・深川花町幼い頃より花街で育ち、酒と笑いの香りに包まれて育つ。
十四の頃から寄席に通いつめ、十八で「花咲亭」を名乗り落語家として初高座を踏む。
「人の世はしょせん、花も笑いも散るものじゃ」と飄々と説くその口調と、膝を叩くように痛快な「花金言」が評判を呼び、江戸から京、大坂へと旅興行を重ねた。「人の世こそ一夜の花盛り」と悟り、その儚さをも愛おしみ、心の言葉を『百花集』として編み上げる。
商いの心、人との縁、暮らしの知恵を話芸に織り込み、町人から大名屋敷まで愛され「福を咲かせる名人」と称された。
「花金言」の記録
覆われている時ほど、内は静かに保たれている。守ることは、止まることではない。
備えの先にこそ、深いひらきが待っておるのじゃ。
寒牡丹(かんぼたん)の守り色――『百花集』より
令和八年 一月 十三日のあなたへ
まだ冷え残る日にも、土の奥は確かに温んでいる。見えぬところで整う時間を、疑わずにいよう。
芽吹きは、信じた分だけ近づくものなのじゃ。
福寿草の土あたたみ――『百花集』より
令和八年 一月 十二日のあなたへ
寒さに身を縮める日にも、芽は迷わず息づいている。進めぬと感じる時ほど、内は整っているもの。
動きは、静けさの底から始まるのじゃ。
節分草(せつぶんそう)のまどい雪――『百花集』より
令和八年 一月 十一日のあなたへ
閉ざされたままのように見える日にも、下では動きが続いている。焦らず、足元の温みを信じればよい。
割れるのは雪だけで、心はゆっくりひらくのじゃ。
雪割草(ゆきわりそう)のひそみ音――『百花集』より
令和八年 一月 十日のあなたへ
まだ硬き朝にも、内には香りが宿っている。急がず、芽の気配に耳を澄ませばよい。
始まりは、静かな予感としてやって来るのじゃ。
白梅のしずかな兆し――『百花集』より
令和八年 一月 九日のあなたへ
本格的に動く前に、深く息を整えればよい。澄んだ心には、次の道が映る。
始め直しは、静かな支度からで十分なのじゃ。
寒菊(かんぎく)の澄み支度――『百花集』より
令和八年 一月 八日のあなたへ
満たすより先に、整える日があってよい。静かに休めば、心は自然に戻ってくる。
労わることも、前へ進む大切な一歩なのじゃ。
七草のひと休み――『百花集』より
令和八年 一月 七日のあなたへ
光ろうとせずとも、日々はきちんと積もっている。見えぬところで支えるものが、暮らしを守る。
足元の確かさを、今日は信じてよいのじゃ。
万両のつや息――『百花集』より
令和八年 一月 六日のあなたへ
抱え込みすぎた日は、重さを静かに下ろせばよい。息が戻れば、足取りも自然に整う。
つづきは、軽くなったところから始まるのじゃ。
千両の息づき――『百花集』より
令和八年 一月 五日のあなたへ
冷えた朝ほど、内側に残る温みを確かめるがよい。急がず歩めば、香りはあとから追いつく。
始まりは、静かなぬくもりで十分なのじゃ。
蠟梅(ろうばい)のほの温み――『百花集』より
令和八年 一月 四日のあなたへ
背筋を伸ばすほどでもなく、俯くほどでもない。ほどよき凛が、心を整えてくれる。
静かな自分に戻れば、歩みはまた自然に始まるのじゃ。
水仙の凛しらべ――『百花集』より
令和八年 一月 三日のあなたへ
にぎやかな後の朝ほど、心は静けさを欲しがる。急ぎ直さず、余韻に身を預けてよい。
整いは、静まりの中から芽を出すのじゃ。
寒椿(かんつばき)の静まり――『百花集』より
令和八年 一月 二日のあなたへ
あらたまる朝には、背筋を伸ばしすぎずともよい。根を確かめれば、伸びる先は自然に定まる。
一歩目は静かでよいのじゃ。
若松の初ひかり――『百花集』より
令和八年 一月 一日(元日)のあなたへ
終わりを数える日には、静かに灯りを守ればよい。過ぎた時は土に還り、次の芽を温めている。
新しき年は、そっと迎えに来るものなのじゃ。
福寿草(ふくじゅそう)の年越し灯――『百花集』より
令和七年 十二月 三十一日のあなたへ
同じ雨に濡れても、色はそれぞれに滲む。比べずともよい。
にじみ出たその色こそ、今日のあなたなのじゃ。
紫陽花のひかり滲み――『百花集』より
令和七年 十二月 三十日のあなたへ
待つことを恐れぬ日には、心が先走らぬ。整うまでの時間も、確かな歩みのひとつ。
白くひらく刻は、静かに選ばれているのじゃ。
浜木綿(はまゆう)の白き待ち――『百花集』より
令和七年 十二月 二十九日のあなたへ
背負いすぎた日は、立ち止まって息を深く。重さを感じた分だけ、手放す先が見えてくる。
歩みは、整った呼吸とともに戻るのじゃ。
石楠花(しゃくなげ)の深き息――『百花集』より
令和七年 十二月 二十八日のあなたへ
固く閉じた時間にも、内側では動きが始まっている。合図は小さくてよい。
気づいた瞬間から、歩みはすでに進んでいるのじゃ。
風信子(ひやしんす)の目覚め音――『百花集』より
令和七年 十二月 二十七日のあなたへ
続けようと気負わぬ日ほど、歩みは長くなる。小さな継ぎ目を大切にすれば、心は途切れぬ。
つづきは、静かな積み重ねの先にあるのじゃ。
桜草(さくらそう)の淡きつづき――『百花集』より
令和七年 十二月 二十六日のあなたへ
境を越えようと急がずともよい。澄んだところに立てば、行く先は自然に見える。
選ぶとは、静けさに身を置くことなのじゃ。
菖蒲(あやめ)の澄みわたり――『百花集』より
令和七年 十二月 二十五日のあなたへ
揺らぎを恥じることはない。細き道ほど、足取りはやさしくなる。
迷いの中でこそ、進む向きは静かに定まるのじゃ。
萩のゆれる径(こみち)――『百花集』より
令和七年 十二月 二十四日のあなたへ
結ぼうと力むほど、ほどけやすくなる。ひと息おけば、心は自然と形を思い出す。
始まりは、静かな呼吸からでよいのじゃ。
朝顔のひと息――『百花集』より
令和七年 十二月 二十三日のあなたへ
思いが揺れる日は、無理に形をつくらずともよい。静けさに身を置けば、心の底にある色がゆっくりと戻る。
深さとは、急がずともにじみ出るものなのじゃ。
葵のかげひそむ碧(あお)――『百花集』より
令和七年 十二月 二十二日のあなたへ
つまずく日があってもよい。ひかりは、足元からそっと差してくる。
ゆっくり整えれば、道はまた続いていくのじゃ。
南天のひかりあし――『百花集』より
令和七年 十二月 二十一日のあなたへ
焦らず歩む日には、心に静かな温もりが灯る。まだ形にならぬ想いも、そっと芽吹いている。
春は、求めすぎずとも近づいてくるものなのじゃ。
沈丁花(じんちょうげ)の春待つ気配――『百花集』より
令和七年 十二月 二十日のあなたへ
力を入れすぎた心は、ふとした拍子にほどけてゆく。流れに逆らわぬ時こそ、息は深くなる。
ゆるむ瞬間を恐れず、そっと受け入れればよいのじゃ。
山吹のしずく音――『百花集』より
令和七年 十二月 十九日のあなたへ
行き先が見えぬ日ほど、香りのような気配に従えばよい。無理に答えを探さずとも、歩みの中で輪郭は浮かぶ。
迷いは、次へ進む前のやさしい合図なのじゃ。
金木犀の路(みち)しるべ――『百花集』より
令和七年 十二月 十八日のあなたへ
忘れまいと力むほど、心は遠くなる。そっと置いておけば、思いは自然に戻ってくる。
大切なものほど、静かに結ばれているのじゃ。
忘れな草の静かな約束――『百花集』より
令和七年 十二月 十七日のあなたへ
強く在ろうとするほど、心は固くなる。余白を残せば、香りは自然と広がっていく。
満たすより、委ねるほうが届く日もあるのじゃ。
山百合(やまゆり)の白き余韻――『百花集』より
令和七年 十二月 十六日のあなたへ
すぐ消えるものほど、朝の心に残る。確かさを急がず、いまの感触を抱けばよい。
はかなさの中にこそ、今日を生きる力が宿るのじゃ。
露草の朝ひかり――『百花集』より
令和七年 十二月 十五日のあなたへ
先を急がぬ心には、気配がよく届く。まだ名のない想いも、静かに息づいている。
兆しは、気づいた者から育てればよいのじゃ。
紫丁香花(ライラック)の淡き兆し――『百花集』より
令和七年 十二月 十四日のあなたへ
胸の奥が詰まる夜ほど、言葉を急がずにいよう。沈黙のあいだに、思いは静かに整っていく。
ひらく時は、無理なく訪れるものなのじゃ。
桔梗(ききょう)のつぼみ――『百花集』より
令和七年 十二月 十三日のあなたへ
手を広げすぎた日は、そっと戻せばよい。抱え直した分だけ、心は軽くなる。
整うとは、足すよりも、休ませることなのじゃ。
撫子(なでしこ)の宵やすらぎ――『百花集』より
令和七年 十二月 十二日のあなたへ
心が曇る日は、光のほうからそっと寄ってくる。急がず、ひと息おけばよい。
やわらぐ時にこそ、明るさは沁みるのじゃ。
木蓮の白あかり――『百花集』より
令和七年 十二月 十一日のあなたへ
寒さに身を縮める日は、無理に踏み出さずともよい。あたたかなものをひとつ抱けば、心はゆっくりほぐれる。
凛と立つ前に、休む時があってよいのじゃ。
山茶花(さざんか)の冬しらべ――『百花集』より
令和七年 十二月 十日のあなたへ
あれこれ抱えた日ほど、水面に身を映すがよい。波立たぬところにこそ、こころは静かに戻る。
深さは急がず、ゆるやかに感じればよいのじゃ。
睡蓮の水のほころび――『百花集』より
令和七年 十二月 九日のあなたへ
静けさを抱く夜ほど、心の奥がやわらぎ出す。急がずともよい。
やすらぎは、そっと寄り添う時に芽吹くのじゃ。
藤袴(ふじばかま)の秋しじま――『百花集』より
令和七年 十二月 八日のあなたへ
心が揺れる日は、立ち止まってもよい。焦らず見渡せば、ゆっくり戻る道がある。
迷うときこそ、ひとつ深呼吸をするのじゃ。
彼岸花のくれない影――『百花集』より
令和七年 十二月 七日のあなたへ
まっすぐ朝を迎えられぬ日もあろう。それでも光は、そっと肩に触れてくれる。
うつむく時間があるからこそ、明るさは沁みるのじゃ。
黄水仙(きずいせん)の朝ゆらぎ――『百花集』より
令和七年 十二月 六日のあなたへ
静けさに寄り添うと、心の形がそっと戻ってくる。急がぬ時間をひとつ抱けば、息の深さが変わる。
整うとは、無理をほどくところから始まるのじゃ。
鈴蘭のしろたえ滴――『百花集』より
令和七年 十二月 五日のあなたへ
張りつめた心も、ふとした温もりにほどけてゆく。強がりをやめた瞬間にこそ、静かな力が芽を出す。
やわらぐ日は、やわらぐままでよいのじゃ。
薄紅梅(うすこうばい)の春ゆらぎ――『百花集』より
令和七年 十二月 四日のあなたへ
急がぬ歩みには、心の声がよく届く。背中を押す風が弱い日ほど、自分の輪郭が静かに戻る。
ゆるやかな時間こそ、人を整えてくれるのじゃ。
花水木のそよぎ筆――『百花集』より
令和七年 十二月 三日のあなたへ
あれこれ抱えた日ほど、立派に見せずともよい。そっと力を抜けば、息の通り道が戻ってくる。
ひらくのは、無理を手放した心からなのじゃ。
芍薬(しゃくやく)のゆらぎ羽――『百花集』より
令和七年 十二月 二日のあなたへ
焦らぬ灯りは、闇を追い立てぬ。静かなぬくもりに寄り添えば、心の影も柔らかくほどける。
明けゆく前にこそ、人はひと息つけるのじゃ。
月見草のまどろみ灯――『百花集』より
令和七年 十二月 一日のあなたへ
たれて落ちる静けさは、心を急がせぬ。背伸びをやめれば、見える景色がひとつ増える。
ゆるむところに、人の本当の強さは宿るのじゃ。
藤のしずく影――『百花集』より
令和七年 十一月 三十日のあなたへ
こらえていた想いも、温もりに触れればふっと緩む。無理に強さを纏わずともよい。
ほどけた瞬間こそ、人はまた歩き出せるのじゃ。
雪柳のほころび音――『百花集』より
令和七年 十一月 二十九日のあなたへ
ひそやかに咲くものほど、声を荒げず、ただ在り続ける。
急がずともよい。静けさに身を置けば、心の芯がゆっくりと戻ってくるのじゃ。
山眠る椿のあたたみ――『百花集』より
令和七年 十一月 二十八日のあなたへ
春を待たずとも、光を見つければそっと開く。時期をはかりすぎずともよい。
あなたの歩みもまた、ふと思い立った一歩から咲きはじめるのじゃ。
白木蓮(はくもくれん)のひらき声――『百花集』より
令和七年 十一月 二十七日のあなたへ
秋桜(コスモス)は、風の強さを計らず、ただ揺れて受け流す。
無理に構えずともよい。撓(たわ)む日こそ、心がほどけるのじゃ。
秋桜(コスモス)の風ゆらぎ――『百花集』より
令和七年 十一月 二十六日のあなたへ
一夜だけ咲く花は、短さを嘆かず全てを輝きに変える。限られた時ほど、心は澄み、想いは強くなるのじゃ。
〝いま〟を尽くす者こそ、美しい。
月下美人の微笑み――『百花集』より
令和七年 十一月 二十五日のあなたへ
つるを伸ばして実を結ぶ花は、遠回りを恥じはせぬ。曲がりくねった道こそ、豊かな実りを運んでくるのじゃ。
迷いの数だけ、人は深くなるのじゃ。
山帰来(さんきらい)のたまゆら――『百花集』より
令和七年 十一月 二十四日のあなたへ
散りゆく花びらも、川面に浮かべば新しき旅人。流されるように見えても、行き先は自ら選んでおる。
身をゆだねる勇気もまた、道をひらく力なのじゃ。
花筏(はないかだ)のゆくえ――『百花集』より
令和七年 十一月 二十三日のあなたへ
深き森の陰に咲く花は、日差しのわずかな切れ目を逃さず、そっと光を集めて息づく。
大きな恵みを待たずとも、小さな光をつなげば、生きる力となるのじゃ。
雪笹(ゆきざさ)のひかり――『百花集』より
令和七年 十一月 二十二日のあなたへ
枝を離れて舞う葉は、散りゆくことを恐れぬ。旅立ちの時を知り、静かに空を描いて落ちるのじゃ。
変化を選ぶ心こそ、つぎの季節を呼ぶ力となる。
秋椛(あきなみき)のささやき――『百花集』より
令和七年 十一月 二十一日のあなたへ
人の影になりがちな花ほど、よく周りを見て咲いておる。
目立たずとも、そっと寄り添うそのやさしさが、誰かの一日を救うのじゃ。
薄紅葵(うすべにあおい)のまなざしの誓い――『百花集』より
令和七年 十一月 二十日のあなたへ
寒さにも暑さにも負けず、常盤椿は一年じゅう緑を絶やさぬ。
変わらぬ心こそが、人を安心させ、支えとなるのじゃ。
常盤椿(ときわつばき)の誓い――『百花集』より
令和七年 十一月 十九日のあなたへ
小さき花びらに宿る光は、太陽よりも強いときがある。
自らを大きく見せずとも、真心があれば、どんな闇にも灯をともせるのじゃ。
金鳳花(きんぽうげ)のひかり――『百花集』より
令和七年 十一月 十八日のあなたへ
風に揺られても散らぬ花は、力で耐えるのではなく、しなやかに受け流す。
折れぬ強さとは、曲がることを恐れぬ心なのじゃ。
山吹の調べ――『百花集』より
令和七年 十一月 十七日のあなたへ
清らかな花ほど、泥を知らぬわけではない。濁りの中でこそ、白さを選んで咲くのじゃ。
環境ではなく、心のありようが人を照らす。
白蓮の言の葉――『百花集』より
令和七年 十一月 十六日のあなたへ
人の影にひっそり咲く花は、光を求めて焦らぬ。
小さき場所でも、自らを信じて咲くならば、そこが春の真ん中になるのじゃ。
紫蘭(しらん)の願い――『百花集』より
令和七年 十一月 十五日のあなたへ
朝の光をうけて咲く露草は、誰よりも短い命を、誰よりも美しく生きる。
永さではなく、いまこの瞬間に心をそそぐこと、それが花の生きざまなのじゃ。
露草のきらめき――『百花集』より
令和七年 十一月 十四日のあなたへ
風に身をまかせて揺れる花薄は、決して折れようとはせぬ。
まっすぐ立つことよりも、しなやかに在ることが、強さなのじゃ。
花薄(はなすすき)のささやき――『百花集』より
令和七年 十一月 十三日のあなたへ
朝に咲き、夕べにしぼむ花は、短さを嘆かず、一日をまるごと生きる。
長さよりも濃さ、時間よりも心──それが人生の花の咲かせ方なのじゃ。
芙蓉(ふよう)の晴れ姿――『百花集』より
令和七年 十一月 十二日のあなたへ
冬空の下で咲く花は、人のぬくもりを待たずとも微笑む。
寒さに負けぬ強さよりも、寒さを受け入れるやさしさが、美を生むのじゃ。
寒桜の微笑み――『百花集』より
令和七年 十一月 十一日のあなたへ
雪の中で咲く花は、春を待たずに己の時を選ぶ。
寒さを恐れず咲くその姿に〝いまを生きる〟という誇りがあるのじゃ。
冬牡丹(ふゆぼたん)の誇り――『百花集』より
令和七年 十一月 十日のあなたへ
〝難を転ずる〟と書いて南天。つらき日も、笑いに変えれば吉となる。
苦しみを避けるより、それを光に変える心が、真の幸運を招くのじゃ。
南天のことづて――『百花集』より
令和七年 十一月 九日のあなたへ
秋の終わりに咲く白菊は、静けさの中でなお香りを放つ。
派手に散らずとも、心に残る余韻こそが、本当の美なのじゃ。
白菊の言の葉――『百花集』より
令和七年 十一月 八日のあなたへ
人に見せるためでなく、寄り添うために咲く花がある。
そのやさしさは声を出さずとも、風にのって心をなでるのじゃ。
桜草(さくらそう)の願い――『百花集』より
令和七年 十一月 七日のあなたへ
細くとも、赤き糸のように咲く花がある。人の縁もまた、見えぬところで結ばれておる。
強く引かず、そっとたぐる心が、長きつながりを生むのじゃ。
水引草(みずひきそう)のつなぎ――『百花集』より
令和七年 十一月 六日のあなたへ
紅に染まる葉も、散るために咲くのではない。最後の一刻まで、美しくあろうとするのじゃ。
終わりゆく時こそ、人の本質があらわれる。
紅葉草のいのち――『百花集』より
令和七年 十一月 五日のあなたへ
雪の下でも息づく芽がある。誰に見られずとも、静かに春を信じて待つ。
忍耐とは止まることではなく、信じつづける力なのじゃ。
雪割草(ゆきわりそう)のちかい――『百花集』より
令和七年 十一月 四日のあなたへ
清き水に根を張る花は、泥を恐れず、美を育てる。
濁りの中にも心を澄ませば、どんな場所でも花は咲くのじゃ。
桜蓮(おうれん)の願い――『百花集』より
令和七年 十一月 三日のあなたへ
散るときも音を立てず、椿は静かに地をうるおす。
別れや終わりを恐れずに、静かに次の命へ渡す姿、それこそが〝しなやかな強さ〟なのじゃ。
花椿(はなつばき)のしぐれ――『百花集』より
令和七年 十一月 二日のあなたへ
人の目に触れず咲く花も、香りを隠そうとはせぬ。評価を求めずとも、ただ〝自分らしく〟咲けばよい。
それで十分、世の中に彩りは増すのじゃ。
花茗荷(はなみょうが)のつぶやき――『百花集』より
令和七年 十一月 一日のあなたへ
秋の風に揺れながらも、花は決してうつむかぬ。
寂しさの中にも凛と立ち、静けさを美に変える。それが秋明菊の生きざまなのじゃ。
秋明菊(しゅうめいぎく)のこころ――『百花集』より
令和七年 十月 三十一日のあなたへ
誰かの足もとに寄り添うように、桜草はそっと咲く。
名を知られずとも、人の笑顔のそばで息づくこと、それもまた花の幸せなのじゃ。
桜草(さくらそう)のしるし――『百花集』より
令和七年 十月 三十日のあなたへ
春まだ浅き風の中でも、黄水仙は顔を上げて咲く。
季節を待たずに笑うその姿は、希望という名の花そのものなのじゃ。
黄水仙(きずいせん)の約束――『百花集』より
令和七年 十月 二十九日のあなたへ
風に揺れても、折れずに笑う花がある。強さとは、耐えることではなく、揺れながらも立ち続ける心なのじゃ。
やわらかさこそ、真の芯の強さなのじゃ。
秋桜(コスモス)のまなざし――『百花集』より
令和七年 十月 二十八日のあなたへ
人の歩みが遅くとも、花は季節を責めはせぬ。それぞれの時に、それぞれの咲き方がある。
あせらずともよい、遅咲きの花ほど、色が深いのじゃ十
秋海棠(しゅうかいどう)の微笑み――『百花集』より
令和七年 十月 二十七日のあなたへ
雨に濡れてこそ、紫陽花は色を深める。晴れの日ばかりでは、本当の美は育たぬのじゃ。
涙のあとの笑顔こそ、人をいちばんやさしくするのじゃ。
山紫陽花(やまあじさい)のこころ――『百花集』より
令和七年 十月 二十六日のあなたへ
日が沈むころに咲く花は、闇を恐れず、静かに灯をともす。
光の少ないときこそ、心のあかりが人を導くのじゃ。
夕桔梗(ゆうききょう)の祈り――『百花集』より
令和七年 十月 二十五日のあなたへ
朝露は陽に溶けて消えるが、その一瞬、花をいちばん美しく見せる。
長く残ることよりも、今を照らす輝きこそ尊いのじゃ。
朝露のひとしずく――『百花集』より
令和七年 十月 二十四日のあなたへ
高き枝にすがらずとも、藤は垂れて咲き、人を見上げさせる。
へりくだる姿の中にこそ、ほんとうの美しさは宿るのじゃ。
藤のかがやき――『百花集』より
令和七年 十月 二十三日のあなたへ
雪を割って咲く紅梅は、寒さを恐れず、色を増す。逆境こそが、その美を深めるのじゃ。
人の心もまた、試練を経てこそ温もりを知るものよ。
紅梅のあかし――『百花集』より
令和七年 十月 二十二日のあなたへ
空に枝を伸ばす花水木は、春の光をいっぱいに受けながら、散るその時まで姿を崩さぬ。
終わりまで美しくあろうとする心、それこそが生きる誇りなのじゃ。
花水木の誓い――『百花集』より
令和七年 十月 二十一日のあなたへ
静かにうつむいて咲く花は、恥ずかしがっているのではない。ひそやかに感謝を祈っているのじゃ。
頭を下げることは、弱さではなく、やさしさのあらわれなのじゃ。
鈴蘭水仙のしずく――『百花集』より
令和七年 十月 二十日のあなたへ
枝をしならせながら咲く雪柳は、重さに耐えることで美しさを増す。
重荷を背負う日があってもよい。それを抱えて進む姿こそ、強さの証なのじゃ。
雪柳(ゆきやなぎ)のしらべ――『百花集』より
令和七年 十月 十九日のあなたへ
背を競わぬ小さき花は、陽の当たる場所を譲り合って咲く。
強さとは争うことではなく、誰かを思いやる余白を持つことなのじゃ。
雛菊(ひなぎく)のまごころ――『百花集』より
令和七年 十月 十八日のあなたへ
道ばたに静かに咲く花は、誰に見られずとも空を仰ぐ。
評価を求めぬその姿は、ひとり歩む者への道しるべとなるのじゃ。
花韮(はなにら)の微笑み――『百花集』より
令和七年 十月 十七日のあなたへ
小さき花でも、色を失わず咲き抜くものがある。華やかでなくともよい、強くなくともよい。
ただ、自分の色を捨てぬことが、生きる誇りなのじゃ。
桜蓼(さくらたで)の志――『百花集』より
令和七年 十月 十六日のあなたへ
散った花びらも流されて終わりではない。川面を進み、新しい景色へたどり着く。
たとえ形を変えても、道は続いておるのじゃ。
花筏(はないかだ)の旅――『百花集』より
令和七年 十月 十五日のあなたへ
踏まれても踏まれても、白詰草は土の上に顔を出す。
強さとは、倒れぬことではなく、何度でも立ち上がる心のことじゃ。
白詰草の誇り――『百花集』より
令和七年 十月 十四日のあなたへ
花びらに見える白き葉は、ほんとうの花を守るために咲いておる。
目に見えるものだけがすべてではない。陰で支える力こそ、花を咲かせるのじゃ。
山法師(やまぼうし)のまなざし――『百花集』より
令和七年 十月 十三日のあなたへ
鈴の音も持たぬ小さき花が、なぜ〝幸福の花〟と呼ばれるのか。
それは、そっと寄り添うだけで人の心をあたためる力があるからじゃ。
鈴蘭のことづて――『百花集』より
令和七年 十月 十二日のあなたへ
思い通りにならぬ日もある。けれど、都忘れの花は嘆かず咲く。
すべてを抱えようとせず、今日の心に似合う静けさを選べばよいのじゃ。
都忘れのやすらぎ――『百花集』より
令和七年 十月 十一日のあなたへ
陽のあたる場所ばかりが春ではない。人知れぬ谷にも、静かに咲く花がある。
光を待たずとも、自らのぬくもりで春を呼ぶのじゃ。
山吹水仙のことば――『百花集』より
令和七年 十月 十日のあなたへ
朝露の中で咲く露草は、陽が昇るとともにしぼむ。
短き命を悔いず、その一刻を澄みきって生きる。これぞ、儚くも尊き美なのじゃ。
露草(つゆくさ)の祈り――『百花集』より
令和七年 十月 九日のあなたへ
人里離れた山の奥でも、桜は誰に見られずとも咲く。
咲くために咲く──それが、真の誇りというものじゃ。
山桜の息吹――『百花集』より
令和七年 十月 八日のあなたへ
雨に打たれても折れぬ花、それが花菖蒲というもの。
美しさは飾りでなく、耐えてなお凛とする心に宿るのじゃ。
花菖蒲(はなしょうぶ)の誓いの誇り――『百花集』より
令和七年 十月 七日のあなたへ
冬の風に散らされながらも、寒椿は凛として咲き続ける。
季節に背を向けず、自らの時を貫く姿こそ、真の誇りというものじゃ。
寒椿(かんつばき)の誇り――『百花集』より
令和七年 十月 六日のあなたへ
風にのって届く香りは、姿を見せずとも人を癒す。
声なき優しさこそ、長く心に残る香となるのじゃ。
金木犀の香――『百花集』より
令和七年 十月 五日のあなたへ
豪華に咲く牡丹も、土に根を張るからこそ崩れぬ。
見える華やぎより、見えぬ支えこそが、花を真にゆるがぬものとするのじゃ。
牡丹のゆるぎ――『百花集』より
令和七年 十月 四日のあなたへ
春を告げる白き木蓮は、寒さを恐れず空を仰ぐ。
人もまた、凍える日々を越えてこそ、未来を信じる力を得るのじゃ。
木蓮の誓い――『百花集』より
令和七年 十月 三日のあなたへ
夜明けとともに咲く朝顔は、わずかな時を惜しまず輝く。
長さを競わず、その瞬間を尽くす姿こそ、人に勇気を与えるのじゃ。
朝顔のつとめ――『百花集』より
令和七年 十月 二日のあなたへ
雪の残る頃にほころぶ梅は、寒さを知るからこそ香り高い。
困難を越えて咲く花ほど、人の心に深く沁みるものなのじゃ。
梅のさとし――『百花集』より
令和七年 十月 一日のあなたへ
小さき花びらを重ねる撫子は、一輪では目立たずとも、群れて咲けば野をやさしく染める。
人の縁もまた、ひとつひとつが集まって、大いなる力となるのじゃ。
撫子のえにし――『百花集』より
令和七年 九月 三十日のあなたへ
道ばたに燃えるように咲く花は、人に踏まれずとも、ただ自らの時を全うする。
人の歩みもまた、誰に認められずとも尊いものなのじゃ。
彼岸花の道――『百花集』より
令和七年 九月 二十九日のあなたへ
山野にひっそり咲く桔梗は、華やかさを求めずとも、深き青で人の心を澄ませる。
大声で示さずとも、静けさにこそ誠は宿るのじゃ。
桔梗のこころ――『百花集』より
令和七年 九月 二十八日のあなたへ
飾らずにただ白く咲く花は、人に媚びることなく、自らの清らかさを示す。
まごころは飾りを要さず、そのままにして尊いのじゃ。
白百合のまごころ――『百花集』より
令和七年 九月 二十七日のあなたへ
秋風にそよぐ萩の花は、声なき声で揺れ続ける。大きな音はなくとも、心ある人には必ず届く。
静けさの中にこそ、深き力があるのじゃ。
萩のこえ――『百花集』より
令和七年 九月 二十六日のあなたへ
秋の野に咲く紫苑は、古より〝思い出〟を伝える花。
過ぎし日を嘆くためでなく、今を大切にするために、人は記憶を抱くのじゃ。
紫苑(しおん)のことば――『百花集』より
令和七年 九月 二十五日のあなたへ
黄金の花びらは小さくとも、一面に咲けば春の山を照らす。
小さき力も、集えば大いなる光となるのじゃ。
山吹のこがね――『百花集』より
令和七年 九月 二十四日のあなたへ
早春に真白き花を空へ向ける木蓮は、寒さ残る風にもひるまず、ただひたすらに天を仰ぐ。
高きを望む心があれば、いまの寒さも道しるべとなるのじゃ。
白木蓮(はくもくれん)の志――『百花集』より
令和七年 九月 二十三日のあなたへ
雪どけの冷たき水に揺れながらも、水芭蕉は澄んだ白を広げて咲く。
困難を抱えた場所こそ、清らかな花を育む土壌なのじゃ。
水芭蕉のしらべ――『百花集』より
令和七年 九月 二十二日のあなたへ
強き風に揺られても、秋桜は倒れずに立ち続ける。
硬さではなく、しなやかさこそが、逆境を越える力なのじゃ。
秋桜のしなやかさ――『百花集』より
令和七年 九月 二十一日のあなたへ
小さき花も群れて咲けば、野を明るく照らす光となる。
ひとりの力は小さくとも、積み重なれば大きな景色を生むのじゃ。
桜草の祈り――『百花集』より
令和七年 九月 二十日のあなたへ
風に揺られて鳴る花の音色は、自ら鳴らそうとしているのではない。
ただ自然にゆだねてこそ、涼やかな響きが生まれるのじゃ。
風鈴草(ふうりんそう)の調べ――『百花集』より
令和七年 九月 十九日のあなたへ
大輪を咲かせる芍薬も、土の下で長く根を張ってきたからこそ輝く。
人の花もまた、見えぬ努力があればこそ、咲くときに堂々とひらくのじゃ。
芍薬(しゃくやく)の凛――『百花集』より
令和七年 九月 十八日のあなたへ
冷たい風の中で咲く花は、凍えるほどの寒さを知っているからこそ、その温もりを人に分け与える。
つらさを抱えた分だけ、やさしさは深くなるのじゃ。
山茶花(さざんか)の灯――『百花集』より
令和七年 九月 十七日のあなたへ
花はやがて実となり、その実は人を癒す薬ともなる。
努力もまた同じこと、すぐに実らずとも、やがて誰かの力となるのじゃ。
花梨(かりん)のしらべ――『百花集』より
令和七年 九月 十六日のあなたへ
まだ春浅きうちに咲く桃は、寒さを恐れず、未来を信じて花をひらく。
いまは頼りなくとも、その兆しがやがて実りへとつながるのじゃ。
早桃(さもも)の兆し――『百花集』より
令和七年 九月 十五日のあなたへ
夕闇にひらく花は、昼の光を知らずとも、自らの時を得て咲く。
人もまた、遅きに見えても、その刻が訪れれば、必ず花開くのじゃ。
夕顔のまどい――『百花集』より
令和七年 九月 十四日のあなたへ
水に映る花は、かたちが揺れても美しさを失わぬ。
人の心もまた、迷いがあってこそ澄んでいくものなのじゃ。
花菖蒲のすがた――『百花集』より
令和七年 九月 十三日のあなたへ
陽に透けて輝く花びらは、散り際まで空を照らしておる。
終わりを恐れず、輝けるときに精いっぱい咲く。それが花の本懐なのじゃ。
紅葉葵(もみじあおい)のひかり――『百花集』より
令和七年 九月 十二日のあなたへ
季節を過ぎても咲く薔薇は、遅れを悔やまず、ただ自分の時を生きておる。
人もまた、早き遅きに惑わされず、自らの歩みを誇ればよいのじゃ。
秋薔薇のあかし――『百花集』より
令和七年 九月 十一日のあなたへ
冬の庭にひっそり咲く花は、派手さはなくとも灯火のようにあたたかい。
大きな声で誇らずとも、静かに咲く姿が、人の心を照らすのじゃ。
石蕗(つわぶき)の微笑み――『百花集』より
令和七年 九月 十日のあなたへ
同じ水辺に咲いていても、一輪ごとに色もかたちも異なる。
比べるためではなく、それぞれが自分の色を映すために咲くのじゃ。
杜若(かきつばた)の彩――『百花集』より
令和七年 九月 九日のあなたへ
里の桜よりも早く散る山桜は、短さを惜しまれながらも、その一瞬を全うして咲く。
長さではなく、どれほど真実に咲いたかが花の誇りなのじゃ。
山桜のいのち――『百花集』より
令和七年 九月 八日のあなたへ
秋風に揺れながら咲く花は、誰かに見てもらうためでなく、ただ季節とともにあるために咲いておる。
人の評価に縛られずとも、生きるだけで充分に美しいのじゃ。
秋明菊のまどい――『百花集』より
令和七年 九月 七日のあなたへ
水面に映る花は、揺らめきながらも美しさを失わぬ。
ゆれる日々こそ、人の心を澄ませる鏡なのじゃ。
杜若(かきつばた)の澄み――『百花集』より
令和七年 九月 六日のあなたへ
雨に打たれても、黄菖蒲は水辺に凛と立つ。濁りの中でこそ、鮮やかに咲こうとする。
環境が清らかでなくとも、自らの色は失わぬものなのじゃ。
黄菖蒲のきざし――『百花集』より
令和七年 九月 五日のあなたへ
小さな花が集まって、まあるい毬となる。一人では小さき光でも、ともに寄り添えば、あたたかな形を結ぶ。
花も人も、支え合うときこそ輝くのじゃ。
小手毬の微笑み――『百花集』より
令和七年 九月 四日のあなたへ
朝に咲き、夕べに散る花もある。けれどその短さを惜しむより、一日のすべてを懸けて咲く姿を愛でたい。
時の長さではなく、どれほど真心を込めたかが花の値打ちなのじゃ。
芙蓉のゆめ――『百花集』より
令和七年 九月 三日のあなたへ
小春の木立に一番に色をつける花は、早さを誇るためではなく、ただ自分の時が来たから咲く。
先に咲くも、遅れて咲くも、花の道に違いはないのじゃ。
花蘇芳(はなずおう)のきざし――『百花集』より
令和七年 九月 二日のあなたへ
水面に映る花は、本当の姿でなくとも美しい。
人もまた、誰かの心に映るとき、思いがけず光を増すことがあるのじゃ。
杜若(かきつばた)の映え――『百花集』より
令和七年 九月 一日のあなたへ
目立たぬ小さき花でも、風にそよぐ音は、耳を澄ませば届く。
小さき声だからこそ、心に深く響くこともあるのじゃ。
撫子のこえ――『百花集』より
令和七年 八月 三十一日のあなたへ
小さき花でも群れて咲けば、蝶を呼び寄せる力を持つ。
ひとりの力は儚くとも、つながりがあれば道は広がるのじゃ。
藤袴のゆらぎ――『百花集』より
令和七年 八月 三十日のあなたへ
椿は音を立てて散るが、その潔さを恥じることはない。
終わりを恐れず咲ききる姿こそ、人の心を澄ませるのじゃ。
椿のしらべ――『百花集』より
令和七年 八月 二十九日のあなたへ
背すじを伸ばして咲く百合は、風に揺れても誇りを失わぬ。
真っすぐであることは、頑なさではなく、自らを信じるやわらかさなのじゃ。
百合のすがた――『百花集』より
令和七年 八月 二十八日のあなたへ
朝にしか咲かぬ露草は、短きときを知りながらも、その青を惜しみなく放つ。
限られた時間こそ、輝きはひときわ強くなるのじゃ。
露草のきらめき――『百花集』より
令和七年 八月 二十七日のあなたへ
ひと息つくときにも、花はその姿をとどめておる。
休むことは止まることにあらず、次に咲くための力を集める時なのじゃ。
桜草のひと息――『百花集』より
令和七年 八月 二十六日のあなたへ
強き風に揺れても、秋桜はしなやかに立っておる。
折れぬ理由は、硬さではなく、やわらかく受け止める力にあるのじゃ。
秋桜の風――『百花集』より
令和七年 八月 二十五日のあなたへ
まだ小さき芽でも、やがては山を彩る葉となる。
はじめは頼りなくとも、芽吹いたその一歩こそ、大きな力の始まりなのじゃ。
早蕨(さわらび)の芽ぶき――『百花集』より
令和七年 八月 二十四日のあなたへ
陰のある場所にこそ咲く花もある。日の当たらぬからとて、その花が色あせるわけではない。
静かな場所でこそ、ひそやかな美しさは際立つのじゃ。
秋海棠(しゅうかいどう)のひかり――『百花集』より
令和七年 八月 二十三日のあなたへ
小さき鉢に咲く花も、空のひろさを夢見て伸びる。
たとえ器が小さくとも、思いの大きさに限りはないのじゃ。
金蓮花のゆめ――『百花集』より
令和七年 八月 二十二日のあなたへ
春を告げる白木蓮は、一気に咲きひらきて、その大きな花で空を明るくする。
思いきって心を開けば、周りもまた照らされるものなのじゃ。
白木蓮のひらめき――『百花集』より
令和七年 八月 二十一日のあなたへ
まだ寒さ残る枝先に、ひとつふたつと花がほころぶ。春は遠いようでいて、すでに始まっておるのじゃ。
小さな兆しを信じる心が、季節を呼び込むのじゃ。
薄紅梅の息吹――『百花集』より
令和七年 八月 二十日のあなたへ
大きな木に咲く花は、空に向かってひそやかに咲く。
人の目に届かずとも、空の青さに映えるその姿は、ひとり立つ強さを物語るのじゃ。
桐のたたずまい――『百花集』より
令和七年 八月 十九日のあなたへ
人に祝われて咲く花もあれば、ひっそりと静かに咲く花もある。
声を上げずとも、その清らかさは時を超えて届くのじゃ。
白菊のしずけさ――『百花集』より
令和七年 八月 十八日のあなたへ
山吹の花は金色に見えても、実をつけることは少ない。それでも人はその輝きを愛でる。
実らずとも、咲くだけで価値があるものがあるのじゃ。
山吹のひかり――『百花集』より
令和七年 八月 十七日のあなたへ
大輪ばかりが人の目を引くが、道ばたに咲く撫子は、その小ささゆえに人を和ませる。
大きさではなく、そっと寄り添う温かさこそ、花の力なのじゃ。
撫子のぬくもり――『百花集』より
令和七年 八月 十六日のあなたへ
満開を過ぎても枝に残る花びらは、散り際の時まで空を見上げておる。
遅れたとしても、最後まで咲ききることにこそ、花の誇りはあるのじゃ。
牡丹桜のゆるし――『百花集』より
令和七年 八月 十五日のあなたへ
人が寝静まった夜に咲く花は、拍手も褒め言葉もなくとも、静かに自分の花をひらく。
輝きは、人の目の前だけで生まれるものではないのじゃ。
月見草の笑顔――『百花集』より
令和七年 八月 十四日のあなたへ
色を変える紫陽花は、その時その時の雨と土に寄り添って咲く。
変わることを恐れぬ心が、移ろいの季節を彩るのじゃ。
紫陽花のゆらぎ――『百花集』より
令和七年 八月 十三日のあなたへ
かたい雪を押しのけて咲く花は、力ずくではなく、時を信じて芽を伸ばす。
耐える日々もまた、咲くための道のりなのじゃ。
雪割草のこころ――『百花集』より
令和七年 八月 十二日のあなたへ
花開く前の木蓮は、固いつぼみの中に春を抱いておる。
見えぬところで育てた時こそ、咲いた瞬間を輝かせるのじゃ。
木蓮のまなざし――『百花集』より
令和七年 八月 十一日のあなたへ
雪の残る土から顔を出す水仙は、春を待たずとも、自分の時を知っている。
まわりがまだ眠っていても、咲けるときに咲くのが花の道じゃ。
水仙の微笑み――『百花集』より
令和七年 八月 十日のあなたへ
冬の風にも負けず咲く寒椿は、強さを誇るために咲いておるのではない。
ただ、この季節に咲けるのが自分だからこそ、静かに花をひらいておるのじゃ。
寒椿のいさおし――『百花集』より
令和七年 八月 九日のあなたへ
忘れたいのに忘れられぬ日がある。けれど都忘れの花は、〝忘れよう〟とせずに、ただ静かに咲く。
忘れることよりも、抱きしめる強さが人にはあるのじゃ。
都忘れのしらべ――『百花集』より
令和七年 八月 八日のあなたへ
道ばたにそっと咲く萩の花は、誰にも見られぬまま散ることもある。
それでも咲くのは、〝見せるため〟ではなく、〝在るため〟じゃ。ただそこに咲いている、それだけで尊いのじゃ。
萩のひかり――『百花集』より
令和七年 八月 七日のあなたへ
誰かのために咲く花は、自分を後まわしにすることがある。
けれど、それでも咲こうとする気持ちは、ちゃんと、自分自身をあたためておるのじゃ。
花かんざしの約束――『百花集』より
令和七年 八月 六日のあなたへ
朝に咲きて、昼にはしぼむ露草も、そのひとときにすべてを懸けて咲いておる。
長く咲くことばかりが立派ではない。限られた時を大切にする姿こそ、花の覚悟なのじゃ。
露草の願い――『百花集』より
令和七年 八月 五日のあなたへ
声にならぬ想いも、風にまかせて届くことがある。言葉が出ぬ日は、無理に語らずともよい。
黙って咲いておる花のように、その想いは、ちゃんと誰かに伝わっておるのじゃ。
薄紅のこゑ――『百花集』より
令和七年 八月 四日のあなたへ
咲くときばかりが花ではない。散ったあとに残る静けさにも、その花の美しさは宿っておる。
余白を大事にできる者こそ、本当に咲いた者なのじゃ。
山茶花の余白――『百花集』より
令和七年 八月 三日のあなたへ
遠くの空を見上げながら咲く花は、いまこの場所でも、未来に向かって咲いているのじゃ。
目の前のことばかりにとらわれず、ときには空を見て咲けばよい。
花水木のまなざし――『百花集』より
令和七年 八月 二日のあなたへ
まっすぐに咲く花ほど、静かに時を選んで咲く。
慌てず、飾らず、凛として風にゆれる姿が、人の心を打つのじゃ。
桔梗のしらべ――『百花集』より
令和七年 八月 一日のあなたへ
まだ寒い中でほころぶ梅は、咲くことそのものが、春の知らせとなる。
あなたが勇気を出したその一歩も、誰かにとっての〝あたたかさ〟となるのじゃ。
梅のほころび――『百花集』より
令和七年 七月 三十一日のあなたへ
言葉にせずとも、香りは届く。
くちなしの花のように、静かに寄り添うだけで、誰かの心を癒すことがあるのじゃ。
くちなしの言葉――『百花集』より
令和七年 七月 三十日のあなたへ
散った花びらも、流れに身をまかせて、やがて誰かの景色をつくる。
終わりと思うたその先に、思いがけず新しい道がひらけることもあるのじゃ。
花筏のゆくえ――『百花集』より
令和七年 七月 二十九日のあなたへ
垂れ咲く藤は、上へ伸びるばかりが道ではないと教えてくれる。
人の歩みもまた、下を向いた日こそ、静かに深く根を張っているのじゃ。
藤の帳――『百花集』より
令和七年 七月 二十八日のあなたへ
足もとに咲く白詰草は、気づかれぬまま踏まれることもある。それでも、また笑うように咲く。
ちいさな輪のなかに、大きなやさしさを秘めておるのじゃ。
白詰草の輪――『百花集』より
令和七年 七月 二十七日のあなたへ
立派に咲こうと気張らずともよい。牡丹の花も、朝露に濡れた姿がいちばん美しいときがある。
万全でなくとも、いまこの瞬間のあなたが、誰かにとっての〝咲きどき〟なのじゃ。
朝露の牡丹――『百花集』より
令和七年 七月 二十六日のあなたへ
誰とも違う道を歩むとき、ふと立ち止まってしまうことがある。
けれど、彼岸花は群れずとも、自らの場所で咲き誇る。道の端に咲くからこそ、見る者の心に残るのじゃ。
彼岸花の微笑み――『百花集』より
令和七年 七月 二十五日のあなたへ
長く咲く花にも、迷いの時はある。けれど、色褪せぬのは迷わなかったからではない。
迷いながらも咲き続けた日々が、その色を深めてくれるのじゃ。
千日紅のたゆたひ――『百花集』より
令和七年 七月 二十四日のあなたへ
小さき歩みでも、咲く花の数は変わらぬ。
はやる気持ちに追われずとも、静かに前へ進む者のそばには、必ずや季節がついてくるのじゃ。
萩の小径――『百花集』より
令和七年 七月 二十三日のあなたへ
泥の中から咲く蓮も、あわてて咲こうとはせぬ。
濁りに染まらぬ強さとは、静けさのなかで磨かれるものじゃ。
蓮のまどろみ――『百花集』より
令和七年 七月 二十二日のあなたへ
報われぬ日が続いたとしても、根の先では、静かに春の準備が始まっておる。
花が咲くより前に、希望という芽が動き始めるのじゃ。
風蘭のたより――『百花集』より
令和七年 七月 二十一日のあなたへ
誰かの言葉が胸に残ることがある。それは、心が応えていた証。
花は音を出さぬが、風に揺れたとき、ふと気づかせてくれるのじゃ。
山吹のこだま――『百花集』より
令和七年 七月 二十日のあなたへ
香りというものは、無理に届けようとせずとも、そっと風にのって届くもの。
人の想いもまた同じ。つよく叫ばずとも、まことならば伝わるのじゃ。
金木犀のまどい――『百花集』より
令和七年 七月 十九日のあなたへ
ときには、咲かぬ日もあってよい。陽の光に背を向けて、そっとつぼみを閉じる日もまた、花の一日。
休むことを、恥じてはならぬ。それもまた、咲くための仕度なのじゃ。
芍薬のうたたね――『百花集』より
令和七年 七月 十八日のあなたへ
人目にふれずとも、野の片隅で咲く花がある。
誰に見せるでもなく、ただまっすぐ空を見上げて咲く。それでじゅうぶん、尊いのじゃ。
野菊のまなざし――『百花集』より
令和七年 七月 十七日のあなたへ
風に吹かれて揺れる秋桜も、根は浅いようでいて折れぬもの。やわらかさを笑われてもかまわぬ。
しなやかに立つその姿が、強さの証なのじゃ。
秋桜のうた――『百花集』より
令和七年 七月 十六日のあなたへ
去りゆくものを見送るときこそ、花はひときわ静かに咲く。
別れに涙がこぼれても、その涙が土を潤し、また新しい芽を育むのじゃ。
花菖蒲の見送り――『百花集』より
令和七年 七月 十五日のあなたへ
忘れられたと思うた日にも、紫苑はそっと咲き続けておる。
人の記憶に残るより先に、自分のために咲くのが花の道じゃ。
紫苑の呼び声――『百花集』より
令和七年 七月 十四日のあなたへ
小さき花ほど、風に揺れてもしなやかに立つ。
折れぬように、かたくなるのではなく、揺れながら根を張るのじゃ。
撫子の約束――『百花集』 より
令和七年 七月 十三日のあなたへ
大きく咲こうとあせることはない。椿の花は、つぼみの間も美しい。
時を待つその静けさこそ、いちばん尊いものじゃ。
紅椿のひそみ――『百花集』 より
令和七年 七月 十ニ日のあなたへ
人知れず寒空に咲く白梅は、誰かに見られようと見られまいと、その香りを惜しまず放つ。
咲く理由を外に探さず、ただ自分の花を咲かせるのじゃ。
白梅の微笑み――『百花集』 より
令和七年 七月 十一日のあなたへ
雨に濡れた花は、咲き姿を崩すこともある。けれど、しおれたように見えても、根は深く息づいておるもの。
晴れ間がのぞけば、また凛と立ち上がるのじゃ。
紫の雨――『百花集』 より
令和七年 七月 十日のあなたへ
散るのを恐れて花は咲かぬか。ひとひらの別れを怖れて、春を迎えぬか。
散ると知りつつも咲くからこそ、その花は人の胸を打つのじゃ。
桜影のひととき――『百花集』 より
令和七年 七月 九日のあなたへ
朝いちばんに咲いた花も、昼にはしぼむことがある。だからといって、その一瞬の輝きが浅いわけではない。
短い命ほど、いっそう鮮やかに咲こうとするものじゃ。
朝顔の雫――『百花集』より
令和七年 七月 八日のあなたへ
咲くのが遅くとも、夜にひらく花もある。人より遅れて芽吹くことを、恥じることはない。
陽の落ちたあとに、ひそやかに香りを放つ花も、それはそれで美しいものじゃ。
夕顔の灯――『百花集』より
令和七年 七月 七日のあなたへ