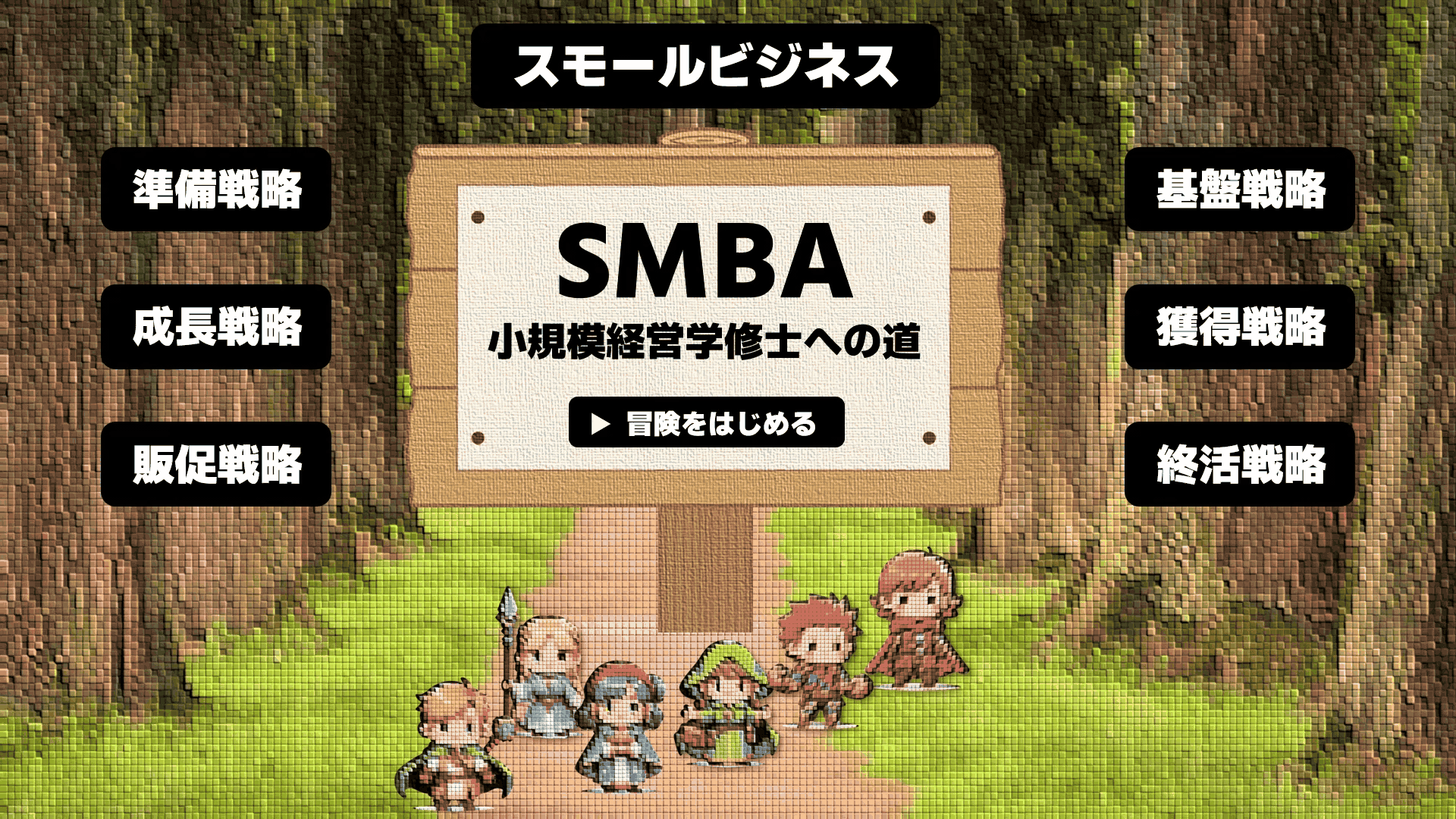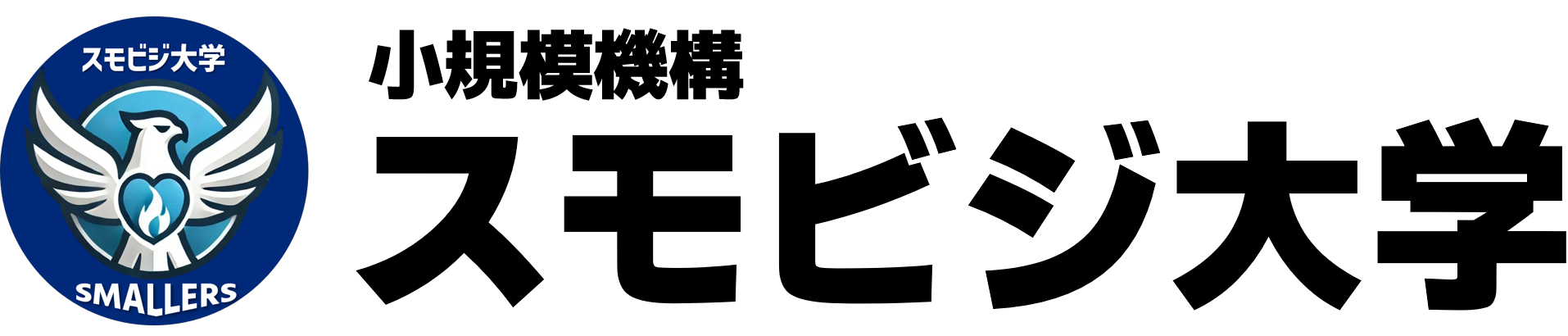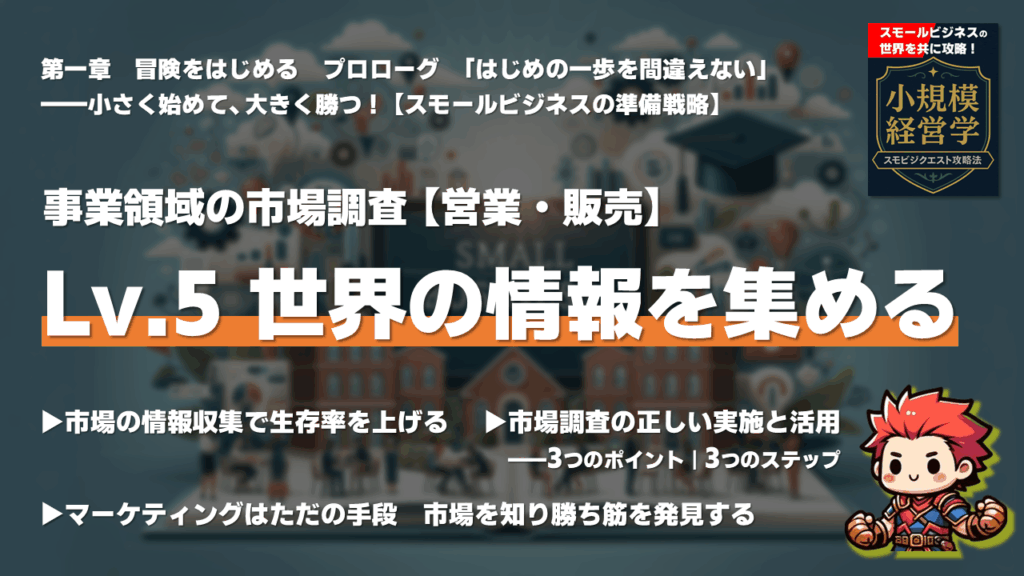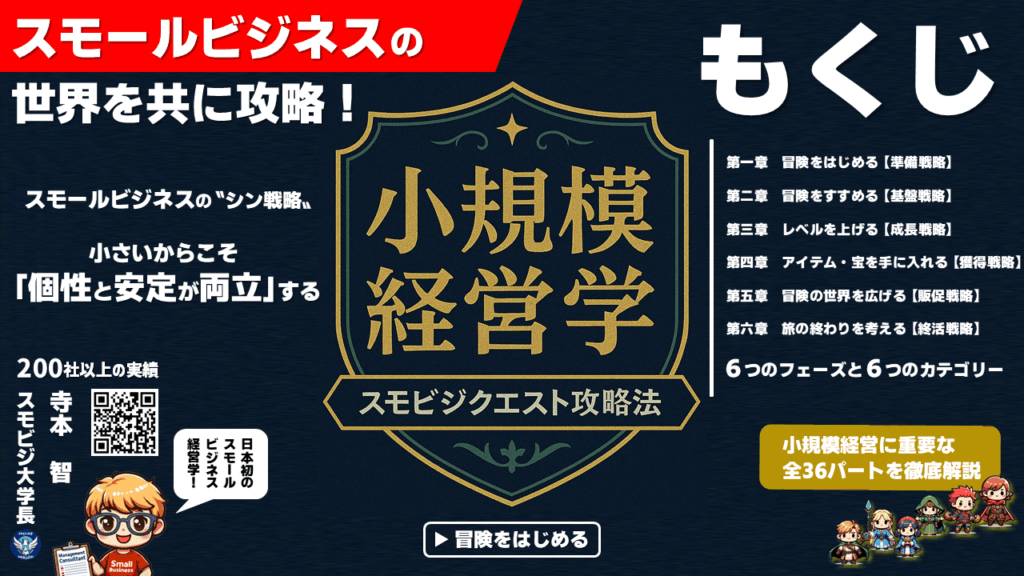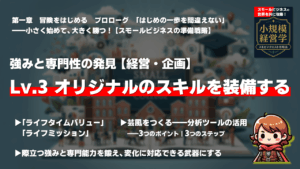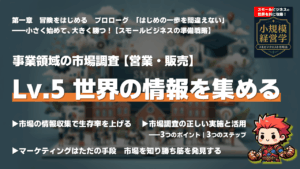Lv.4 旅路のお金を準備する/起業の資金調達方法【お金・財務会計】|小規模経営学
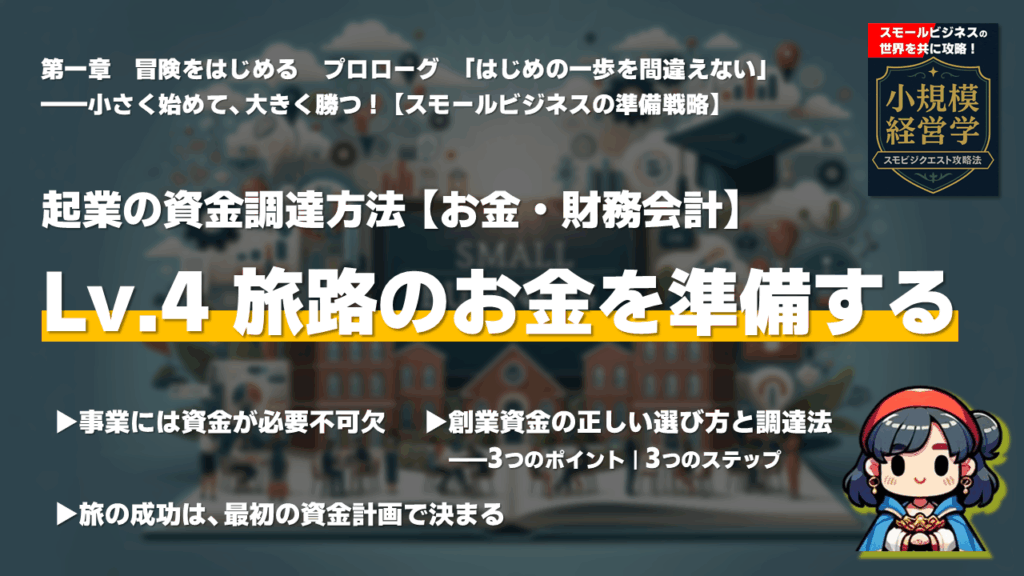
小規模でも事業という旅には、資金が必要不可欠
スモールビジネスをはじめるとき、多くの人は「少額で始められる」と考えがちです。確かに、スモールビジネスは比較的低コストでスタートできます。しかし、どれだけ小さくても「資金」という燃料なしにビジネスを動かすことはできません。
「資金がなければ、旅は始まらない」
ビジネスを旅にたとえると分かりやすいでしょう。行き先(ビジョンや目標)を決め、必要な荷物(リソースやスキル)を準備し、ときには寄り道やトラブルにも対応しながら進んでいく――。
この旅を成功させるには、距離やルートに応じた「燃料=資金」が欠かせません。どんなに素晴らしいアイデアや計画を持っていても、それを実行するための資金がなければ、旅の途中で立ち往生してしまうのです。
なぜ「旅」にたとえるのか?
事業のスタートは、まさに「旅のはじまり」です。旅の準備をするとき、行き先を決め、荷造りをし、交通手段を考えますよね。ビジネスも同じです。
- 目的地(ビジョン・目標)を決める
- 必要な装備(スキル・知識)を揃える
- ルートを計画する(事業計画・マーケティング)
- 燃料(資金)を準備する
資金がなければ、旅は始められません。車がガソリンなしでは走れないように、事業も資金なしでは前に進めません。小規模ビジネスだからこそ、限られた資源を最大限活用し、戦略的に資金を確保することが求められます。
事業は、行き先を決め、仲間を集め、トラブルを乗り越えながら目的地へ向かう――それはまるでRPGゲームのようなもの。だからこそ〝資金〟という燃料が欠かせないのです。次にナビゲーターとして仲間に加わるのは、【お金・経理担当】の〝ファイナン〟です。
次にナビゲーターとして仲間に加わるのは、【お金・経理担当】の〝ファイナン〟です。

資金を燃料にたとえると、とてもわかりやすいわ。ありがとう! ファイナン

事業も旅も同じ。資金という燃料がないと続かないのよね
小規模だからこそ、資金の使い道が重要
大規模ビジネスと違い、小規模ビジネスでは資金の使い方が経営の成否を決定づけます。少ない資金でも最大の効果を発揮するために、ムダを省き、最も重要な部分に投資する必要があります。
✔ 資金計画を立てる
「どこに、どれくらいのお金を使うのか?」を明確にし、優先順位を決めることが大切です。スモールビジネスの初期に必要な資金は、大きく分けて次の3つです。
1 設備投資:店舗やオフィスの内装や設備、パソコンや機材の購入など
2 運転資金:事業を軌道に乗せるまでの人件費、材料費、光熱費など
3 マーケティング費用:広告、ウェブサイト作成、SNSプロモーション、市場調査など
「この費用をどうやって準備すればいいのか?」と悩むのは当然のこと。とくにスモールビジネスでは自己資金が限られているケースが多いため、適切な資金調達方法を理解し、戦略的に準備する必要があります。計画的に貯蓄をし、資金を準備することは不可欠です。しかし、それだけでは不十分なケースがあるのも現実です。
事業という旅の成功は、最初の資金計画で決まる――あなたの事業が順調に進むよう、創業の準備をしっかり整えましょう。
創業資金は、正しく選び、正しく調達する――スモールビジネスの資金戦略 3つのポイント
1)〝良い事業計画〟をつくる!
資金調達の成否は、事業計画にかかっています。金融機関や出資者にとって、あなたの事業計画は未来への地図そのもの。
「この人に資金を託せば安心だ」と思わせる計画がなければ、満足のいく融資や投資を得るのは難しいでしょう。逆に、曖昧な計画しか示せなければ、不安を与えるだけでなく、融資や投資を断られる可能性が高まります。
融資審査で事業計画がなぜ重要か?
「資金を何に使い、どう回収するのか?」金融機関があなたに、必ず問いかけることです。この問いに明確な答えを提示できなければ、創業資金の調達は困難になるでしょう。
たとえば、銀行が貸し出す資金は、その金融機関の預金者の大切な財産であり、単なるビジネスチャンスの提供ではありません。返済の確実性が審査の最大のポイントとなるため、事業の詳細が書かれた根拠ある資料をもとに、金融機関を納得させる必要があります。

お金のことはやっぱり不安で心配だわ…

そのために計画的な準備が必要なのよ
事業計画の役割とは?
事業計画書は、単なる計画書ではなく、資金を動かすため〝証明書〟といえます。
そこには、「どのように事業を展開し、どのように売上げ、収益を確保するのか」を明確に示すことが求められます。つまり、収支の整合性や将来性を論理的に説明することで、「この事業に融資しても大丈夫」と判断してもらうのです。
「売上予測はどのような根拠で算出したのか?」「運転資金はどの程度必要か?」「返済原資はどこから確保するのか?」――これらの質問に根拠をもって説明できなければ、融資の審査を通過することは難しいでしょう。
資金を調達するためには、次のポイントなどを明確にする必要があります。
- 売上予測:どのような商品やサービスを提供し、どれだけの売上が見込めるのか?
- 収支計画:必要経費や利益がどの程度なのか?具体的な数字を示す。
- マーケット分析:ターゲット顧客や市場のニーズをどれだけ理解しているか?
金融機関にとって、貸し出した資金が適切に運用され、確実に回収されることが最も重要です。ただの数字の羅列ではなく、「現実的で実行可能な計画」であること――融資を受ける側としては、ただ「お金を借りたい」と考えるのではなく、「金融機関にとってのリスクをどう解消するか」という視点を持つことが必要です。
※事業計画書の作成については、✓【Lv.6 冒険の計画書をつくる】で、詳しく解説します。
2)複数の選択肢を持つ
資金調達において、「一つの選択肢」に頼ることは、リスクを高めるだけです。融資を断られた場合のリスクヘッジ、より良い条件での資金調達のためにも、選択肢を広げることが重要になります。

金融機関の選択肢を複数持つことが大事なの?

複数の選択肢を持つことで、余裕のある冷静な判断ができるのよ
選択肢を広げることで得られるメリット
✔ リスク分散:一つの金融機関に頼らないことで、万が一の拒否や条件変更の影響を軽減
✔ 交渉力の向上:複数の機関を比較することで、より有利な条件を引き出せる
✔ 最適な資金調達が可能:事業のステージや特性に応じた最適な方法を選べる
主な資金調達の選択肢
- 信用金庫:小規模事業者にとって、信用金庫や公的融資はハードルが低く、最初の資金調達手段として適している
- 日本政策金融公庫:創業時の資金調達に特化した政府系金融機関、低金利で借りやすい
- クラウドファンディング:市場のニーズを確認しながら資金調達ができる
- インターネット専門銀行:スピーディーな手続きが魅力。「GMOあおぞらネット銀行」など、法人向け独自プランを提供する銀行も注目されています。
- エンジェル投資家・ベンチャーキャピタル:リスクを取れる投資家からの資金調達
資金調達において、「選択肢を持つ」ということは、不確実な未来に対する保険を持つことと同じです。一つの選択肢に固執せず、柔軟に他の方法を模索する姿勢は、経営の安定性と成長を支える重要な要素となります。
自分の事業に合った資金調達手段を組み合わせ、柔軟な戦略を立てましょう。
3)早めに動き始める
資金調達は「時間との勝負」です。融資の審査や手続きには、想像以上に時間がかかることがあるため、事業開始の数か月前から準備を始めることが成功のカギとなります。
なぜ早めの行動が重要か?
✔ 金融機関の審査には時間がかかる
✔ 計画の修正や追加資料の提出が求められる場合がある
✔ 余裕を持って準備することで、より良い条件で交渉できる
日本政策金融公庫や信用金庫の創業融資では、「計画性」が重視されます。「いますぐ資金が必要!」ではなく、「半年後にはこうなっていたい」という計画のもとに資金調達を進めるのが理想的です。
開業6か月前:事業計画作成、4か月前:金融機関と相談、2か月前:融資申請など具体的なタイムラインを持てば、より行動しやすくなります。
資金調達は、「正しい手順」で進めれば怖くない。創業資金は、ただ借りるものではなく、戦略的に確保するものなのです。
3つのステップ
スモールビジネスの資金調達は、戦略的に選択肢を組み合わせること。では、その方法を3つのステップで具体的に紹介します。
①「特定創業支援」を活用する
スモールビジネスのスタート時、資金調達の際に最も重要なのは「確実な資金調達の土台」を築くことです。そこで有効なのが「特定創業支援制度」です。この制度を活用することで、創業融資や税制優遇、補助金などの特典を受けられるため、資金調達のハードルが大きく下がります。
特定創業支援を活用するメリット
✓ 登録免許税の軽減
→ 例:株式会社設立時の登録免許税が半額(通常15万円 → 7.5万円)に
✓ 創業融資が受けやすい
→ 信用保証協会の保証枠が拡大し、無担保・無保証人でも融資が可能に
✓ 補助金申請の優遇
→「小規模事業者持続化補助金」の創業枠を活用し、最大200万円の補助を受けられる
特定創業支援を活用する流れ
1 市区町村・商工会議所に相談:各自治体の創業支援セミナーや講座の情報を入手
2 対象講習を受講(約1~2か月):事業計画の作成、資金調達のノウハウなどを学ぶ
3 支援証明書を取得:講習修了後に発行される証明書をもとに、各種優遇措置を申請

こんなにメリットがある制度って知らなかったわ!

知らない人も多いよね。お得な制度なので、ぜひ活用してほしいわ
「特定創業支援」は、単なる補助金・融資のための手続きではなく、事業を軌道に乗せるための実践的な学びの場でもあります。創業直後の経営リスクを減らし、確実なスタートを切るために、必ず活用しましょう。対象自治体によって、細かな条件が異なります。あなたが支援を受けようとする自治体への確認は忘れずに。
② 最適な金融機関を選び、複数の組み合わせも視野に入れた資金戦略を構築する
スモールビジネスの資金調達では、自社の特性に合った金融機関を選ぶことが大切です。すべての金融機関が同じ条件で融資を提供するわけではなく、それぞれの特徴を理解し、最適な選択をすることが重要です。
1.地域密着型の金融機関(信用金庫・地方銀行)
信用金庫・地方銀行はスモールビジネスの強い味方
✓ 融資の柔軟性
・都市銀行よりも小規模企業の実情に理解があり、経営状況や地域貢献度を評価して融資を検討
✓ 信頼関係の構築
・担当者と継続的にコミュニケーションを取ることで、追加融資や経営相談もスムーズ
✓ 経営支援サービスが充実
・融資だけでなく、税務・経営相談や専門家とのマッチング支援を受けられる
2.日本政策金融公庫
スモールビジネス向けの公的融資の王道
✓ 無担保・無保証人でも融資可能
・民間の金融機関に比べ、創業時の実績が乏しくても融資を受けやすい
✓ 低金利での融資
・政府系機関のため、市場金利よりも低めの利率設定
✓ 長期的な資金計画に最適
・返済期間が長めに設定されており、創業時のキャッシュフローを安定させることができる
3.インターネット専門銀行
スピーディーでスムーズな新時代の金融機関
✓ 手続きがオンライン完結
・店舗に行く必要がなく、審査もスピーディー(最短1日)
✓ 低コストで利用可能
・店舗運営コストがないため、金利や手数料が低め
✓ 独自の融資プラン
・例:「GMOあおぞらネット銀行」では、スモールビジネス向けの特別融資プランを提供
融資を組み合わせて活用することで、資金調達のリスクを分散できます。
✓ たとえば…
- 初期資金は信用金庫で借入れし、地域密着の支援を受ける
- 短期の運転資金はネット銀行で調達し、手続きの負担を軽減
- 本命の創業資金は日本政策金融公庫を活用し、安定した資金計画を立てる
最適な金融機関を選び、事業に合った資金調達を計画しましょう。

いろいろな選択肢があるのね。ある意味安心だわ

スモールビジネスらしく、金融機関選びも柔軟に取り組むことが秘訣ね
③ 創業融資は「日本政策金融公庫」を本命にする
スモールビジネスの創業融資を考える際、最も優先すべきは「日本政策金融公庫」です。実績がなくても利用しやすく、低金利で公的な信頼性があるため、スモールビジネスの資金調達には最適な選択肢となります。
日本政策金融公庫を活用する理由
✓ 無担保・無保証人でも借りやすい
✓ 低金利・長期融資が可能
✓ 創業時の実績がなくても審査が通りやすい
融資を受けるためのポイント
「事業計画書がカギ」
融資審査では、「事業計画書」の内容が最も重視されます
- 売上予測を明確にする
→ 収益モデルが具体的であるほど、審査に通りやすくなる - 資金の使い道を詳細に記載する
→ どのような用途で資金を活用し、事業を成長させるのかを説明 - 創業動機を明確にする
→ なぜこの事業を始めるのか? 経営者としての強みや情熱を伝える - 返済計画をしっかり立て
→ どうやって返済していくかを緻密に計画し伝える
保証協会付き融資をセカンドオプションに
「日本政策金融公庫の融資だけでは不安…」その場合は、保証協会付き融資を活用
- 民間の金融機関と連携し、より多くの資金を調達できる
- 複数の金融機関に分散することで、資金リスクを軽減できる
こうした組み合わせにより、無理のない資金調達が実現し、事業の成功への土台が築かれます。公庫と保証協会を上手に活用し、創業時の資金調達を効率的に進めましょう。
ここで気をつけなければならないポイントは、自己資金ゼロでの融資申請は、現実的ではないということです。
この手法は「スジが良い」とはいいづらく、融資の実行可能性も極めて低くなるのが実情です。仮に資金調達ができたとしても、自己資金がまったくない状態では、その後の資金繰りや運営が一気に苦しくなります。
金融機関からの信頼を得て、安定したスタートを切るためにも、最低でも調達希望額の1/4程度は自己資金として準備しておくのが現実的であり、安定的な経営スタートの目安です。
とはいえ、こうした融資に関する姿勢は、近年少しずつ変化しています。とくに代表者の連帯保証を求めない融資方針が広がりつつあり、金融機関でもその実績が着実に伸びてきています。これは小規模経営にとって非常に重要な変化であり、とても意義のあることだといえます。

代表者個人が連帯保証することが少なくなってきてるの?

そうなの。この変化は小規模経営にとって本当に良い傾向なのよね
また、「商工中金(商工組合中央金庫)」の活用がスモールビジネスの分野でも着実に広がりを見せています。
日本政策金融公庫と同様に政府系の金融機関でありながら、これまでは民間金融機関を補完する役割が中心でした。しかし、中小企業の「メインバンク」としての位置づけを視野に入れた方針転換も進められており、その存在感が高まっています。
スモールビジネスにおいても、商工中金を一つの有力な資金調達先として検討する価値は十分にあるでしょう。
資金調達は事業の話であると同時に、スモールビジネスオーナーである「あなた自身」と「家族」の未来を守るための手段でもあります。〝自分たち〟を守る準備として、いまから真剣に取り組んでいきましょう。
旅の成功は、最初の資金計画で決まる
旅に出るとき、あなたは何を最初に準備しますか?
地図、目的地、持ち物、そして最も大切なのが、旅費=予算です。スモールビジネスという「冒険の旅」にたとえると、ライフや〝HP〟といっても過言ではありません。
どんなに想いがあっても、どんなに良いアイデアがあっても、「資金」という予算計画なしに出発してしまえば、燃料切れで立ち往生してしまうことになります。
つまり、最初の資金計画が、その旅の未来を大きく左右するのです。
資金計画とは、経営の「地図」と「時間表」である
スモールビジネスにとっての資金計画とは、単に「いくら必要か?」という話ではありません。
✓ どのタイミングで
✓ 何に使い
✓ どう回収していくか?
この一連の流れを可視化することが、事業の設計図の一部にもなり、行動のタイムラインにもなります。
資金の調達と使い道は、未来を先読みする力です。だからこそ、最初の設計が曖昧だと、途中で道に迷う可能性が高くなるのです。
「使う」ことより、「残す」ことに意識を向ける
資金調達がうまくいくと、人は少し気が大きくなります。
「これでひと安心!」とばかりに、気前よく使ってしまう。けれども、それは旅の始まりでしかない。
スモールビジネスでは、キャッシュ=「生命線」だからこそ、「どれだけ残すか?」「いかに耐えるか?」という視点が重要です。
✓ 何が起きても3か月は持ちこたえられる資金繰り
✓ 思ったように売上があがらなくても、次の一手を打てる資金の余白
✓ 突発的な出費にも耐えられる最低限の備え
それらすべては、最初の資金計画で決まります。またお金をいざ「使う」ときは、その使いどころが勝敗を分けます。「お金を使う順番と意味」がとても大切ですし、何より限られた予算で運営するのが、小規模経営です。
お金が少ないからこそ、お金の使い道で差が出る。
これがスモールビジネス最大のリアルであり、同時に最大のチャンスでもあるのです。
資金計画は「希望」ではなく、「戦略」である
「なんとかなるだろう」では、経営は進みません。経営における資金計画とは、夢や希望を書く場所ではなく、現実と戦略をすり合わせる場所です。希望や期待値では、家族を守るには不十分です。スモールビジネスでは、事業の失敗=人生への影響がとても大きいです。連帯保証や借入れの責任は、経営者個人にのしかかったりもします。
だからこそ、甘い見通しや希望的観測ではなく、「現実的で、持続可能な資金計画」を持つことが、経営者自身とその家族を守る最大の準備なのです。資金調達は、ただ「お金を用意する」だけではありません。
その資金を、どのように活かすのか?どう使い、どう守り、どう育てるのか?
その計画こそが、スモールビジネスの「生命線」になります。だからこそ、旅の成功は、最初の資金計画で決まる――。
希望だけで出航せず、数字という地図を持ち、冷静な判断と熱い情熱を持って、あなたのスモールビジネスという冒険に、しっかりと備えてください。
それでは、次のレベルへご案内します。
↓ もくじはこちらから ↓
寺本 智(てらもと さとし)
小規模経営学者│スモビジ大学長│小さいからこそ「個性と安定が両立」する『小規模経営学』を体系化│スモールビジネス分野で、教育・コンサルティング・小説を執筆│スモールビジネスコンサルタントとして、10年以上にわたり、従業員0人から20人まで(商業・サービス業は基本5人以下)の小規模企業を200社以上サポート。
活動理念は、『小さな事業を大きな主役へ』。一人ひとりが持つ個性と、経済的な安定。この2つが両立する――そんな〝小さな経営の在り方〟と、スモールビジネスを200社以上サポートした実体験から得た、「小さくても大きな成果を導くことができる」独自の文法を、小規模事業の【6つのフェーズ】と【6つのカテゴリー】に合わせて体系化。
ビジョンは、小さな事業が大きな主役となり、『個性と安定が、両立する社会』――「一億総スモールビジネス」。
▶ スモビジ大学のプログラム

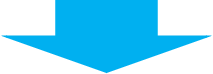
↓ 画像をクリック ↓